英和例文問題 / 中級英単語(CEFR-J B1) - 未解答
中級英単語の含まれる英文を読んで、正しい意味を答える問題です。例文で単語を覚えたい方におすすめです。
- B2: 中上級レベル。一般的な文脈で使われる単語であり、読んだり聞いたりしても自然に理解できるレベルです。
- 「lifelong」は他の品詞(例えば名詞や動詞)としては基本的に使われません。
- life(人生 / 生/いのち)
- long(長い)
- life(名詞): 人生、生命
- lifelong learner(「生涯学習者」の意)
- lifelong learning(「生涯学習」の意)
- lifelong friend → 生涯の友
- lifelong ambition → 生涯の大望
- lifelong passion → 生涯をかけた情熱
- lifelong commitment → 生涯の約束 / 献身
- lifelong dream → 生涯の夢
- lifelong goal → 生涯に渡る目標
- lifelong habit → 生涯の習慣
- lifelong partner → 生涯のパートナー
- lifelong membership → 生涯会員資格
- lifelong learning → 生涯学習
- life: 古英語「līf」
- long: 古英語「lang」
この2つが結びついて「一生の間続く」という意味に発展しました。 - 口語: “He’s been my lifelong friend.” など比較的カジュアルに使われます。
- 文章: エッセイや学術的な文章でも「生涯にわたる影響」のように使われる場合があります。
- attributive use(前置修飾): “He is my lifelong friend.”(彼は私の生涯の友です。)
- predicative use(述語修飾): 稀ですが “This commitment is lifelong.”(この約束は一生ものだ。)というように用いられる場合もあります。
- “He’s been my lifelong friend since we were kids.”
(子どもの頃からの生涯の友なんだ。) - “I’ve had a lifelong love of reading.”
(読書は、生涯を通じて大好きなことなんです。) - “She finally achieved her lifelong dream of writing a novel.”
(彼女はついに小説を書くという生涯の夢を叶えた。) - “Our company aims to build lifelong relationships with clients.”
(当社はお客様との生涯にわたる関係構築を目指しています。) - “He described his lifelong dedication to the field of marketing.”
(彼はマーケティング分野への生涯の献身を語りました。) - “We offer lifelong membership to our exclusive service.”
(当社の特別サービスには生涯会員資格を提供しています。) - “Researchers study the lifelong effects of environmental factors on health.”
(研究者は健康に対する環境要因の生涯にわたる影響を研究しています。) - “Lifelong education is crucial for adapting to a rapidly changing world.”
(急速に変化する社会に適応するためには生涯学習が不可欠です。) - “The curriculum is designed to foster lifelong learning in students.”
(そのカリキュラムは学生に生涯学習を促すよう設計されています。) - permanent(永久の):ずっと存在する点を強調するが、一生というよりも「恒久的」という響きが強い
- enduring(持続する・不変の):外部からの影響に左右されず続く意味合い
- long-term(長期的な):一生に限らず、長期間という点を強調
- temporary(一時的な):短期間だけ続く
- short-lived(短命の):続いてもごく限られた期間
- 発音記号 (IPA):
- イギリス英語: /ˈlaɪf.lɒŋ/
- アメリカ英語: /ˈlaɪf.lɔːŋ/
- イギリス英語: /ˈlaɪf.lɒŋ/
- イギリス英語では「ロング」の部分が /lɒŋ/(「オ」より少し広めの音)
- アメリカ英語では /lɔːŋ/(「オー」に近い音)
- スペル: “lifelong” を “life-long” とハイフンを入れるケースがありますが、通常は一語で書きます。
- 類似表現: “long life” とは逆(「長生き」)ですので取り違えに注意。
- 発音: “life” の後にすぐ “long” をつなげて発音する。
- 混同: “live long” (長生きする)と混同しないように注意しましょう。
- “life” + “long” = 「人生を通して長い」→ 「生涯にわたる」と覚えるとイメージしやすいです。
- 「人生(life)」と「長さ(long)」がつながっているため、スペルのミスをしないように “lifelong” を一語で書きましょう。
- 「一生の友、一生の夢」など大切な価値や長い継続を表すときによく使うので、感情面でも印象的に覚えられます。
- 英語: “massive” = very large in size, amount, or degree; very imposing or impressive
- 日本語: 「非常に大きい」「巨大な」「圧倒的に大きな」などを表す形容詞です。
たとえば「ものすごく大きい建物」や「大規模な影響」に対して使われます。「とても迫力がある」「ずっしりと重厚な」というニュアンスを含む場合が多いです。 - 形容詞 (adjective)
- 原形: massive
- 副詞形: massively (例: “She was massively successful.”)
- 名詞形: massiveness (例: “The massiveness of the mountain was intimidating.”)
- “mass” (名詞) …「かたまり、質量、集団」など
- “massive” は “mass” の形容詞形ですが、もともとの接尾語 “-ive” が付いて、「~の性質を持つ」という意味を作り出しています。
- B2(中上級)
「massive」は日常会話や文章などさまざまな場面で比較的よく使われる語ですが、ニュアンスを理解した上で使い分けるには中上級程度のレベルが目安といえます。 - 語幹: “mass” –「かたまり」「量」を表す
- 接尾語: “-ive” –「~の性質を帯びた」「~のような」の意
- “mass” (名詞)
- “massively” (副詞)
- “to amass” (動詞) …「蓄積する」「大量に集める」
これらは「塊」「大きな量」というニュアンスでつながっています。 - massive attack(大規模攻撃)
- massive building(巨大な建物)
- massive amount of data(膨大なデータ量)
- massive crowd(大群衆)
- massive impact(大きな影響)
- massive scale(巨大な規模)
- massive success(大成功)
- massive changes(著しい変化)
- massive fraud(大規模詐欺)
- massive explosion(大爆発)
- 「massive」はラテン語の “massivus(かたまり(mass)が由来)” にさかのぼり、「重厚な」「ぎっしり詰まった」という意味合いがあります。英語に取り入れられてからは「巨大な」「大規模な」という意味で広く使われてきました。
- 「massive」は単に「大きい」というよりは、「圧倒的な存在感がある」「重厚で迫力がある」といったニュアンスを強く含みます。
- 口語でも文章でも幅広く使いますが、フォーマルな文章でも比較的問題なく使われます。
- “massive + [名詞]” の形で最もよく使われます。
例: “That is a massive project.” - 直接的なイディオムはあまり多くありませんが、“on a massive scale” は「大規模に」という表現としてよく使われます。
- どちらの文脈でも使えます。カジュアルな会話では「ものすごく大きいよ!」という感情表現として、ビジネスや学術的文脈では「大規模なプロジェクト」「大きい影響」などを指す正確な語として使われます。
- 形容詞なので、修飾する名詞の前につけるのが基本です (“massive building”)。
- 比較級・最上級を作る場合は、通常 “more massive” や “most massive” のように、前に “more/most” をつけて作ることが多いです(あまり頻繁には使わない表現ですが)。
- I just got a massive pizza for dinner!(夕食にものすごく大きなピザを買ってきたよ!)
- That concert last night was massive – so many people showed up.(昨夜のコンサートはすごかったよ。ものすごい人が来たんだ。)
- We have a massive pile of laundry to do this weekend.(今週末は洗濯物が山のようにあるよ。)
- Our company is planning a massive product launch next quarter.(当社は来四半期に大規模な商品発売を計画しています。)
- We saw a massive increase in sales after the new campaign started.(新しいキャンペーンが始まってから、売り上げが大幅に増加しました。)
- The project requires a massive budget to be completed successfully.(このプロジェクトを成功させるには、膨大な予算が必要です。)
- The researchers discovered a massive cluster of galaxies in the distant universe.(研究者たちは遠方の宇宙で巨大な銀河群を発見しました。)
- Their study reveals a massive discrepancy between the theory and the data.(彼らの研究は、理論とデータとの間に大きな不一致があることを示しています。)
- A massive body of evidence supports this new hypothesis.(膨大な証拠がこの新しい仮説を裏付けています。)
- huge(とても大きい)
- enormous(非常に大きい)
- colossal(巨大な)
- gigantic(非常に大きい)
- immense(計り知れないほど大きい)
- “massive” は特に「重さ」や「圧倒感」を強調することが多いです。
- “enormous” は「広大さ・数の多さ・程度の大きさ」で強調する場合に多用されます。
- “gigantic”“colossal” は「巨大物」を強くイメージさせる語感があります。
- tiny(とても小さい)
- minuscule(ごくごく小さい、極小)
- slight(わずかな)
- IPA(アメリカ英語): /ˈmæs.ɪv/
- IPA(イギリス英語) : /ˈmæs.ɪv/
- 強勢(アクセント)は第一音節 “mas-” に置かれます。
- “massive” の “-ive” は「イヴ」のように発音されます。
- アメリカ英語・イギリス英語を通して音の違いはそれほど大きくありませんが、アメリカ英語では “mæs” の /æ/ がやや平べったい音になる傾向があります。
- スペルミスとしては “masive” と “s” を一つ抜かしてしまうケースがありますが、正しくは “massive” です。
- 同音異義語は特にはありませんが、 “massif”(地理学で使われる「山塊」)と混同しないように注意が必要です。
- TOEIC・英検などの試験では、“massive investment”、“massive growth” などビジネスシーンで頻出する表現として出題される可能性があります。
- 「mass(塊)」が「大きな固まり」というイメージを持つので、「massive」は「塊のように大きい」と覚えるとわかりやすいです。
- スペリングは “mass” + “ive” を意識して、「マス(塊)+イヴ」と音で分けてイメージすると記憶しやすいでしょう。
- 使うときは「圧倒的な大きさ」を強調したい場合に便利な形容詞であることを思い出すとよいです。
- 英語: An official document issued by a government, certifying the holder’s identity and citizenship and entitling them to travel under its protection to and from foreign countries.
- 日本語: 政府が発行する公式の身分証明書であり、外国へ出入国する際に必要となる書類。自国民であることを証明します。
- A2(初級): 旅行で使う頻度が高く、初級レベルでも知っておきたい語彙。
- pass + port
- “pass” は「通る・通過する」の意味
- “port” は「港」や「入り口、門戸」の意味
- もともと「港や国境を通過する許可書」というニュアンスが含まれています。
- “pass” は「通る・通過する」の意味
- passport control: 入国審査(パスポートチェック)
- passport photograph / passport photo: パスポート写真
- passport office: パスポートの申請・発行を行う役所
- renew a passport(パスポートを更新する)
- apply for a passport(パスポートを申請する)
- passport control(入国審査)
- passport holder(パスポート所持者)
- passport number(パスポート番号)
- carry a passport(パスポートを携帯する)
- valid passport(有効なパスポート)
- expired passport(期限切れのパスポート)
- biometric passport(生体認証対応パスポート)
- passport photo(パスポート写真)
- 中世フランス語の “passeport” が語源とされ、 “passer”(通過する)+ “port”(港)の組み合わせで、「港を通過するための許可状」という意味でした。そこから国境を通過するための許可証へと意味が発展しています。
- フォーマル/カジュアルな文脈: 一般的にオフィシャルな文脈で使われる言葉ですが、旅行の話などカジュアルな場面でも頻出します。
- 感情的な響き: 自国民としての身分証明という公式感がありますが、日常会話で使っても堅苦しさはありません。
- 可算名詞 (countable noun): 通常は “a passport” / “two passports” のように数えられます。
- 一般的な構文: “I forgot my passport.” / “Make sure you have your passport ready.” のように目的語や所有物として用いられることが多いです。
- “to show (one’s) passport”: パスポートを提示する
- “to check (someone’s) passport”: パスポートを確認する
- “Don’t forget to pack your passport before you leave for the airport.”
(空港へ向かう前に、パスポートを忘れずに荷物に入れてね。) - “I can’t find my passport anywhere. I might have left it at home.”
(パスポートがどこにもない… 家に置いてきたかもしれない。) - “When does your passport expire?”
(あなたのパスポートはいつ有効期限が切れるの?) - “Please submit a copy of your passport along with the visa application.”
(ビザ申請書と一緒にパスポートのコピーも提出してください。) - “We need your passport details for the international conference registration.”
(国際会議の登録にパスポート情報が必要です。) - “Make sure your passport is valid for at least six months before your business trip.”
(出張前に、パスポートの有効期限が少なくとも 6 ヶ月残っているか確認してください。) - “Proof of identity, such as a valid passport, is required to attend the symposium.”
(シンポジウムに参加するには、有効なパスポートなどの身分証明書が必要です。) - “The research analyzes the historical significance of passports in international law.”
(この研究では、国際法におけるパスポートの歴史的意義を分析しています。) - “Applicants must present a government-issued passport to verify their nationality.”
(志願者は、国籍確認のために政府発行のパスポートを提示しなければなりません。) - travel document(旅行証明書)
- 一般的に海外へ出るための書類を指す総称として使われる。パスポートだけでなく、その他の渡航書類も含みうる。
- 一般的に海外へ出るための書類を指す総称として使われる。パスポートだけでなく、その他の渡航書類も含みうる。
- ID card(身分証明書)
- 身分証明書全般を指すが、海外渡航には原則としてパスポートの方が公式性が高い。
- 身分証明書全般を指すが、海外渡航には原則としてパスポートの方が公式性が高い。
- 明確な反意語はありませんが、 パスポートを不要とするような “免許不要 (免除)” などの概念は “visa waiver” のように表現する場合もあります。直接の対義語ではないので注意が必要です。
- 発音記号 (IPA)
- アメリカ英語: /ˈpæspɔːrt/ または /ˈpæs.pɔːrt/
- イギリス英語: /ˈpɑːspɔːt/
- アメリカ英語: /ˈpæspɔːrt/ または /ˈpæs.pɔːrt/
- アクセントの位置: 最初の “pass” の部分に強勢がきます (PASS-port)。
- アメリカ英語とイギリス英語の違い:
- アメリカ英語では “pæ”(パァ)のように発音し、r の音がしっかり発音されがちです。
- イギリス英語では “pɑː”(パー)と長めに母音を発音し、語尾の “r” はあまり強く発音されません。
- アメリカ英語では “pæ”(パァ)のように発音し、r の音がしっかり発音されがちです。
- スペルミス: “pasport” のように “s” を一つしか書かないミスが多いです。正しくは “passport” (s が2つ)。
- 分割してしまう: “pass port” などとスペースを入れないように注意。
- 同音異義語との混同: 同音異義語や類似単語は特にありませんが、“pasteboard” など似た形の単語と混同しないように注意。
- 試験対策: TOEIC や英検などで、海外出張・旅行に関する場面設定のリスニング問題やリーディング問題などで登場する可能性があります。書類や身分証に関する記述として出ることが多いです。
- 「pass(通過する)+port(港)」= 港を通過するための書類 → 旅のための必須アイテム というイメージで覚えると便利です。
- スペルの s が二つあることを意識しながら、「パス + ポート」で切れ目を入れると覚えやすいでしょう。
- 実際に旅行に行く際は常に持ち歩くので、実物と結びつけて覚えると定着しやすいです。
- A1(超初心者)やA2(初級)レベルの学習者にとっては少し馴染みが薄いかもしれませんが、日常会話や文章に出てくることが多い重要単語です。
- 名詞なので動詞のような活用はありません。複数形は「breasts」です。
- 同じ語幹から来ている派生表現としては動詞の「to breast (something)」=「胸で押し分ける、立ち向かう」のような古風な用法もあります。
- 接頭語や接尾語というより、古英語“brēost”に由来する一語です。
- 接辞の明確な追加はありませんが、「breastfeed (母乳で育てる)」や「breaststroke (平泳ぎ)」などの複合語として用いられます。
- 人体の胸部、特に女性の乳房。
- 鳥の胸肉(料理用語)。
- 心臓のあるあたり、胸(全般)を表す文学的表現。
- breast cancer(乳がん)
- breast milk(母乳)
- chicken breast(鶏の胸肉)
- breast tissue(胸部組織)
- breast pocket(胸ポケット)
- breast bone(胸骨)
- breast stroke(平泳ぎ)
- breast-feeding(授乳)
- bare one’s breast(s)(胸をあらわにする)
- keep something close to one’s breast(自分の胸に秘める ⇒ 秘密にしておく)
- 古英語“brēost”から派生し、ゲルマン語派に起源をもつとされています。胸や乳房を指す意味は古くから大きく変わっていません。
- 「breast」は比較的直接的に身体的な意味を指すため、文脈によってはセンシティブな印象を与える場合があります。カジュアルな会話でも医療や育児(breastfeeding)に関する文脈では頻繁に用いられます。一方、フォーマルな文章では「chest」という単語や「bust」という単語が使われることもあります。
- 可算名詞です。単数形「breast」、複数形「breasts」。
- (動詞用法)「to breast the waves (波に胸を向ける)」など古風な・比喩的表現で使われることがありますが、現代ではあまり一般的ではありません。
- フォーマル/カジュアル:身体的な部位なので、カジュアルな場面で人の胸を指すなら「chest」を用いることも少なくありません。特に女性の胸について話す際は話題の取り扱いに注意が必要です。
- “She found a lump in her breast.”
- 自分の胸にしこりを見つけた。
- 自分の胸にしこりを見つけた。
- “He gently placed his hand on his breast.”
- 彼は胸にそっと手を当てた。(文学的・フォーマルなニュアンス)
- “I prefer chicken breast to chicken thigh.”
- 「私は鶏もも肉よりも胸肉のほうが好きです。」
- 「私は鶏もも肉よりも胸肉のほうが好きです。」
- “I need a bra that supports my breasts.”
- 「胸をしっかり支えてくれるブラジャーが必要です。」
- 「胸をしっかり支えてくれるブラジャーが必要です。」
- “She pressed the baby against her breast.”
- 「彼女は赤ちゃんを胸に抱き寄せました。」
- “Our hospital specializes in breast cancer treatment.”
- 「当院は乳がんの治療を専門としています。」
- 「当院は乳がんの治療を専門としています。」
- “There will be a fundraiser for breast cancer research next month.”
- 「来月、乳がん研究のための資金集めイベントが行われます。」
- 「来月、乳がん研究のための資金集めイベントが行われます。」
- “We’re launching a new campaign for breast health awareness.”
- 「当社は胸の健康への意識を高めるための新しいキャンペーンを開始します。」
- “Breast tissue density is an important factor in assessing cancer risk.”
- 「胸部組織の密度は、がんのリスクを評価する上で重要な因子です。」
- 「胸部組織の密度は、がんのリスクを評価する上で重要な因子です。」
- “Recent studies show a correlation between diet and breast health.”
- 「最近の研究では、食生活と乳房の健康との間に関連があることが示されています。」
- 「最近の研究では、食生活と乳房の健康との間に関連があることが示されています。」
- “The mammogram revealed an abnormality in her left breast.”
- 「マンモグラフィで彼女の左胸に異常が見つかりました。」
- chest(胸):男女共に使える一般的な胸の表現。
- bust(胸囲・胸部):主に女性の胸を指すが、サイズ的なニュアンスが強い。
- bosom(胸):やや古風・文学的・感情的なニュアンスがある。
- 胸部の反意語というものは特にありませんが、「back(背中)」は身体の前と後ろという対比の観点では対になることがあります。
- 発音記号(IPA): /brɛst/
- アメリカ英語: ブレス(子音の/r/を強めに発音する傾向)
- イギリス英語: ブレスト(アメリカ英語とほぼ同じですが、/r/が控えめ)
- 強勢は第1音節(breast)の「bre」にきます。
- よくある間違い:スペルは “breast” であって、“brest” ではないことに注意。(a が入る)
- スペリングミス
- “breast”を“brest”や“breas”などと書き間違える人がいます。
- “breast”を“brest”や“breas”などと書き間違える人がいます。
- 発音上のまぎらわしさ
- 末尾の -st をはっきり発音しましょう。
- 末尾の -st をはっきり発音しましょう。
- 同音異義語との混同
- 同音異義語はほとんどありませんが、「breath(呼吸)」や「breathe(息をする)」と似たスペリングなので混同しないようにしましょう。
- 同音異義語はほとんどありませんが、「breath(呼吸)」や「breathe(息をする)」と似たスペリングなので混同しないようにしましょう。
- 試験対策
- TOEICや英検で直接出題される機会は多くありませんが、医療や健康に関する話題や、料理で「chicken breast」が登場する場合は重要単語となります。
- “breast”の “a” を忘れないように
- 「胸のブレスは ‘a’ を含む」とイメージするとスペリングミスを防ぎやすいです。
- 「胸のブレスは ‘a’ を含む」とイメージするとスペリングミスを防ぎやすいです。
- 料理の場面を連想する
- 「スーパーで買う“チキンBREAST(胸肉)”」をイメージすると覚えやすいです。
- 「スーパーで買う“チキンBREAST(胸肉)”」をイメージすると覚えやすいです。
- “chest”との使い分け
- “breast”はより直接的に乳房のニュアンスが強い、特に女性に対して使われることが多い。より広い意味での「胸」は“chest”でカバーできると覚えておくと良いでしょう。
- “breast”はより直接的に乳房のニュアンスが強い、特に女性に対して使われることが多い。より広い意味での「胸」は“chest”でカバーできると覚えておくと良いでしょう。
- 原形: historical
- 比較級: more historical
- 最上級: most historical
- 名詞形: history (歴史)
- 副詞形はありませんが、「歴史的に〔言えば〕」のように言いたい場合は “historically” (副詞) となります。
- B1 (中級): よく使われる形容詞の一つですが、日常会話では初歩的な学習段階でも触れる機会があるため、B1くらいのレベルを想定するとよいでしょう。
- 語幹: histor- (history と同じ語幹)
- 接尾語: -ical (形容詞を作る接尾語)
- history (名詞): 歴史
- historic (形容詞): 歴史的に重要な(特に記念碑的・世紀的な出来事を強調するイメージ)
- historically (副詞): 歴史的観点から、歴史的に
- “historic” は「歴史的に重要な、画期的な」という意味合いが強い
- “historical” は「歴史に関する、過去の出来事に関する」というニュアンス
- historical event(歴史的出来事)
- historical figure(歴史上の人物)
- historical context(歴史的文脈)
- historical records(歴史資料)
- historical artifacts(歴史的遺物)
- historical background(歴史的背景)
- historical drama(歴史ドラマ)
- historical site(歴史的名所)
- historical perspective(歴史的視点)
- historical novel(歴史小説)
- 語源: “history” はギリシャ語の “historia”(探求、知識からの学習)に由来し、“-ical” は形容詞を作るラテン系の接尾語が転用されたもの。
- 歴史的使用: 古くから学術分野や公式文書で使われてきましたが、今では日常的に「過去に関する」「歴史上の」という文脈でも広く使われます。
- “historical” はどちらかと言えば「ただ過去に起こった事柄に関係する」という客観的なイメージです。
- 口語でも文章でも使えますが、フォーマルな論文やレポートなどでも頻用される、汎用性の高い単語です。
- 注意: “historic” は「歴史上重要な・画期的な」というニュアンスを伴うため、“historical” と混同しないようにしましょう。
- 形容詞なので、名詞を修飾する位置で使います。
- 基本的に限定用法 (a historical document) と叙述用法 (The document is historical) 両方で使えます。
- 可算・不可算の意識は必要ありません(形容詞のため)。
- 場合によっては強調構文や比較級などに使えます。
- in historical perspective: 歴史的視点に照らして
- from a historical standpoint: 歴史的見地から
“I love visiting historical sites when I travel.”
(旅行に行ったときは歴史的な名所を訪れるのが大好きなんだ。)“That museum has a lot of historical artifacts from the ancient times.”
(あの博物館には、古代の歴史的遺物がたくさん展示されているよ。)“Are you interested in historical dramas on TV?”
(テレビでやっている歴史ドラマに興味はある?)“We based our marketing strategy on historical sales data.”
(私たちは過去の販売データを基にマーケティング戦略を立てました。)“Understanding the company's historical performance is crucial for future planning.”
(会社のこれまでの業績を理解することは、将来の計画のためにとても重要です。)“The report includes a historical analysis of market trends over the last decade.”
(レポートには、過去10年にわたる市場動向の歴史的分析が含まれています。)“A historical overview of the region's political changes is provided in this paper.”
(この論文では、その地域の政治的変遷に関する歴史的概要を提供しています。)“Historical evidence suggests that climate variations impacted ancient civilizations.”
(歴史的証拠によれば、気候変動が古代文明に影響を与えた可能性があります。)“We need to examine the historical documents to verify the authenticity of these claims.”
(これらの主張の真偽を確かめるために、歴史的な文書を調査する必要があります。)historic(歴史的に重要な)
例: “This is a historic moment for the country.”(これはその国にとって歴史的に重要な瞬間です。)ancient(古代の)
例: “The city is known for its ancient ruins.”(その都市は古代の遺跡で有名です。)legendary(伝説的な・伝説上の)
例: “He’s a legendary figure in local folklore.”(彼は地元の民間伝承では伝説的な人物です。)- 厳密な反意語はありませんが、文脈によっては “modern” (現代の) や “contemporary” (現代の) が対比的に使われることがあります。
- 発音記号 (IPA): /hɪˈstɒr.ɪ.kəl/ (イギリス英語), /hɪˈstɔːr.ɪ.kəl/ (アメリカ英語)
- アクセント(強勢): 2つ目の音節 “-stor-” に主なストレスが置かれます。
- イギリス英語: hi-STOR-i-cal
- アメリカ英語: hi-STOR-i-cal
- イギリス英語: hi-STOR-i-cal
- よくある間違い: “history” と同じように “HIStorical” と読んでしまう誤りがありますが、正確には「hi-STOR-i-cal」というリズムになります。
- historic と historical の混同:
- “historic”: 歴史的に重要な
- “historical”: 歴史に関係する、単に過去に関する
- “historic”: 歴史的に重要な
- スペリングミス: “historical” を “historical” 以外の形にしてしまうミス (例: “historacal” のように書いてしまう)
- 同音異義語は特にありませんが、アクセントや “historic” と短縮形にしたときの使い分けに注意が必要です。
- 試験対策: TOEIC や英検などのリーディングで、“historic” と “historical” の違いを問う問題が出る可能性があります。
- h+i+STOR+y + -ical → historical
“h+i+ストーリー的な語幹 + -ical” で、「歴史に関する」と覚えるのも手です。 - 「history」を知っていれば「historic/historical」は派生語と結びついて覚えやすくなります。
- ストーリー (story) と関連づけて覚えると、「過去のストーリー(歴史)に関する」というイメージになり、記憶しやすいでしょう。
- 英語: waste, trash, garbage, or rubbish
- 日本語: ごみ、廃棄物
- B2(中上級): 日常英語や一般的なトピックは理解できるが、文章表現になるとやや難しく感じるレベル。
「refuse」は日常会話ではあまり聞かれないため、中上級者が理解していると便利な単語です。 - refusal (n.): 断り
- refuse (v.): 断る(アクセント・発音が異なる)
- refuse collector (n.): ごみ収集者(= ごみ収集車運転手など)
- refuse collection (n.): ごみ収集
- household refuse (家庭ゴミ)
- dispose of refuse (ゴミを処理する)
- refuse collection (ゴミ収集)
- refuse bin (ゴミ箱)
- refuse disposal (ゴミ処分)
- organic refuse (有機性廃棄物)
- municipal refuse (市のゴミ、都市ごみ)
- industrial refuse (産業廃棄物)
- refuse bag (ゴミ袋)
- recycling refuse (ゴミのリサイクル)
- フランス語 “refuser” から。もともとは「拒否する」という意味ですが、英語では名詞として「不要になったもの・捨てられるもの」という意味を持つようになりました。
「ごみ」や「廃棄物」を表現するのに、“trash”や“garbage”よりもややフォーマル・文書的な響きがあります。政府系文書や公的なごみ収集の案内などで使われることが多いです。
日常会話ではあまり使われず、文章や少し堅い場面で“refuse”という名詞を見かける場合があります。
不可算名詞 (uncountable noun)
- 通常は “refuse” と単数形のまま扱われます。
- “refuses” として複数形を取ることはまずありません。
- 通常は “refuse” と単数形のまま扱われます。
文中での使用例
- “Refuse is collected every Monday.”(ごみは毎週月曜日に収集されます)
- 冠詞は通常つきませんが、特定の文脈で“the refuse”と使われることもあります(「特定の廃棄物」というニュアンス)。
- “Refuse is collected every Monday.”(ごみは毎週月曜日に収集されます)
フォーマル/カジュアル
- “refuse (n.)”はややフォーマルな響きがあるため、日常会話では“trash” や “garbage” の方が一般的です。
- 公的機関の文書や書面でよく使われる傾向にあります。
- “refuse (n.)”はややフォーマルな響きがあるため、日常会話では“trash” や “garbage” の方が一般的です。
- “Could you take out the refuse before you leave?”
(出かける前にゴミを出してくれない?) - “I forgot to put the refuse bags outside last night.”
(昨晩、ゴミ袋を外に出すのを忘れてしまった。) - “The kitchen is starting to smell because of the piled-up refuse.”
(たまったゴミが原因で台所からにおいがしてきたよ。) - “The company needs a better system for handling industrial refuse.”
(その会社は産業廃棄物を処理するための、より良いシステムが必要だ。) - “We have to comply with local regulations regarding refuse disposal.”
(私たちは、ゴミ処理に関する地域の規制を遵守しなければなりません。) - “Please separate recyclable materials from general refuse.”
(リサイクル可能な素材と一般ゴミを分別してください。) - “The urban development study emphasized sustainable methods of refuse management.”
(その都市開発研究では、持続可能なゴミ管理の方法が強調された。) - “Accurate data on refuse composition is vital for environmental impact assessments.”
(環境影響評価においては、ゴミの組成に関する正確なデータが不可欠だ。) - “The municipality enacted new policies to reduce the total volume of refuse produced.”
(その自治体は、排出されるゴミの総量を減らすための新政策を施行した。) - trash (n.): アメリカ英語で一般的に「ゴミ」を指す。日常会話でよく使われる。
- garbage (n.): アメリカ英語で主に「生ごみ」などの湿ったゴミに使われる傾向がある。
- rubbish (n.): イギリス英語で一般的に「ゴミ」を指す。アメリカ英語話者はあまり使わない。
- waste (n.): 「廃棄物」全般に広く使われるが、より抽象的でリサイクルや環境に焦点を当てる文脈で多用。
- “valuables” (価値のあるもの), “possessions” (所有物) などが文脈によっては対になる場合もありますが、直接的な反意語はありません。
名詞 “refuse”: /ˈrɛfjuːs/
- 第一音節「re-」にアクセントが来る。
- アメリカ英語でもイギリス英語でも /ˈrɛfjuːs/ が一般的。
- 第一音節「re-」にアクセントが来る。
動詞 “to refuse”: /rɪˈfjuːz/
- 第二音節「-fuse」にアクセントが来る。
- 同じスペルだが、発音位置と意味が全く異なるので注意。
- 第二音節「-fuse」にアクセントが来る。
- 動詞と混同して /rɪˈfjuːz/ と発音してしまうミスがあるので要注意。名詞の場合は /ˈrɛfjuːs/。
スペルは同じでも動詞形と名詞形の意味と発音が異なる
- 名詞 “refuse”: /ˈrɛfjuːs/ → 「ごみ」
- 動詞 “refuse”: /rɪˈfjuːz/ → 「断る」
ここを混同すると会話で誤解を与える可能性があります。
- 名詞 “refuse”: /ˈrɛfjuːs/ → 「ごみ」
同音異義語との混同は少ないが
- 文脈によっては完全に意味が変わるため、品詞をしっかり見極めましょう。
試験対策
- TOEICや英検などで “refuse” が動詞か名詞か区別させる問題が出ることがあるかもしれません。
- 特にリスニングではアクセント位置の違いが理解度の鍵です。
- TOEICや英検などで “refuse” が動詞か名詞か区別させる問題が出ることがあるかもしれません。
- 「re- = 再び, fuse = 注ぐ」という語源的なイメージから派生してきた単語ですが、実際には名詞として「不要物・廃棄物」を意味します。
- 覚えるコツとしては、ゴミを「テーブル(レフ)の上に(stat.fuse) 置く」と想像して、「アクセントが前に来る方が名詞」と覚えると区別しやすいかもしれません。
- 動詞と名詞の発音の違いを意識して、“I refuse to collect refuse.”のような文を作ってみると、忘れにくくなります。
- 英語での意味: “The time in the morning when the sun appears or begins to rise above the horizon.”
- 日本語での意味: 「太陽が水平線上に昇り始める時刻のこと」
品詞: 名詞 (可算名詞として扱うことが多い)
- 【単数形】sunrise
- 【複数形】sunrises (あまり頻繁には使われませんが、複数の「日の出のシーン」を指したいときなどに用いられます)
- 【単数形】sunrise
派生的な形:
「sunrise」は基本的には名詞のみとして使われます。動詞化・形容詞化は一般的ではありません。
参考として「sun」(太陽)+「rise」(昇る)と分解できますが、「sunrising」などの派生形は通常存在しません。難易度目安(CEFR): A2(初級)
簡単な表現や日常場面でよく出てくる単語です。時刻や自然現象に関する日常英会話で頻繁に使われます。語構成:
- sun: 「太陽」
- rise: 「昇る」
この2つの語が組み合わさって、「太陽の昇るとき(太陽が昇ること)」という意味を表しています。
- sun: 「太陽」
関連語・類縁語:
- dawn(夜明け,暁): 太陽が昇る直前あたりの薄明かりを指す。
- daybreak(夜明け): dawn とほぼ同義で、日が明ける頃。
- sunset(日没): 太陽が沈むとき。対になるような語。
- dawn(夜明け,暁): 太陽が昇る直前あたりの薄明かりを指す。
よく使われるコロケーション(共起表現)や関連フレーズ(10個)
- watch the sunrise(日の出を見る)
- at sunrise(日の出の時に)
- a beautiful sunrise(美しい日の出)
- just before sunrise(日の出直前)
- sunrise over the mountains(山の上からの日の出)
- sunrise ceremony(日の出に合わせた式典)
- an early sunrise(早めの夜明け/早い時期の夜明け)
- spectacular sunrise(壮観な日の出)
- sunrise view(日の出の眺め)
- break of dawn / break of day(夜が明けるころ、日の出あたり)
- watch the sunrise(日の出を見る)
語源:
「sun」は古英語の “sunne” に由来し、「rise」は古英語の “rísan” に由来します。英語においては、非常に古くから「太陽が昇る」様子を表す言葉として定着しています。ニュアンスや使用時の注意点:
- 「sunrise」は、視覚的・感覚的に「日の出」という明るいイメージを伴うため、詩的表現にもよく使われます。
- カジュアルな会話からフォーマルな文章まで幅広く使われますが、文学的・ロマンチックなトーンを出すのにも適しています。
- 「sunrise」は、視覚的・感覚的に「日の出」という明るいイメージを伴うため、詩的表現にもよく使われます。
可算名詞 / 不可算名詞:
一般に「日の出」をひとまとまりの現象として表すため、可算名詞として捉えられ、「a sunrise」「the sunrise」のように冠詞を付けて使うことが多いです。複数形 “sunrises” は稀に、異なる場所や異なる日の「日の出」を指す場合に使うことがあります。一般的な構文やイディオム:
- “see the sunrise” / “watch the sunrise”: 「日の出を見る」
- “rise at sunrise”: 「日の出と同時に起きる」
- “from sunrise to sunset”: 「日の出から日没まで」(丸一日中という意味合い)
- “see the sunrise” / “watch the sunrise”: 「日の出を見る」
使用シーン:
- カジュアル: “Let’s get up early and watch the sunrise!”
- フォーマル: “The sunrise over the horizon was a truly breathtaking sight.”
- カジュアル: “Let’s get up early and watch the sunrise!”
“I love watching the sunrise on the beach.”
(私はビーチで日の出を見るのが大好きなんだ。)“What time is sunrise tomorrow?”
(明日の日の出は何時かな?)“I usually go for a jog at sunrise.”
(私はいつも日の出の頃にジョギングに出かけます。)“Our team will start the photoshoot at sunrise to get the best light.”
(私たちのチームは最高の光を得るため、日の出と同時に写真撮影を始めます。)“We’re planning a company retreat that includes a sunrise yoga session.”
(我が社では、日の出ヨガセッションを含む会社の研修を計画中です。)“The new promotional video captures the city skyline at sunrise.”
(新しいプロモーション動画では、日の出時の街のスカイラインが映し出されています。)“According to the meteorological data, sunrise will occur at 5:48 AM.”
(気象データによると、日の出は午前5時48分に起こります。)“This study focuses on the effects of sunrise light on human circadian rhythms.”
(この研究は、人間の概日リズムにおける日の出の光の影響に焦点を当てています。)“Historical accounts confirm that the fortress was attacked just after sunrise.”
(歴史的記録によると、その要塞は日の出直後に攻撃されたことがわかっています。)類義語
- dawn(夜明け)
- 「 faint light before sunrise 」のことを強調。太陽が顔を出す前の薄明り。
- 「 faint light before sunrise 」のことを強調。太陽が顔を出す前の薄明り。
- daybreak(夜明け)
- 「夜の終わりを告げて一日が始まるとき」。dawn とほほ同義。
- 「夜の終わりを告げて一日が始まるとき」。dawn とほほ同義。
- morning twilight(薄明)
- 主に科学用語的に「太陽が昇る直前の空の薄明かり」。
- 主に科学用語的に「太陽が昇る直前の空の薄明かり」。
- dawn(夜明け)
反意語
- sunset(日没): 太陽が沈むとき。
- sunset(日没): 太陽が沈むとき。
ニュアンスの違い
- “sunrise” は太陽の光が見え始める瞬間そのものに焦点を当てているのに対し、 “dawn” は光が差し始める時間帯のイメージが強いです。
発音記号(IPA):
- 米音: /ˈsʌnˌraɪz/
- 英音: /ˈsʌn.raɪz/
- 米音: /ˈsʌnˌraɪz/
アクセントの位置:
- “SUN-rise” のように、最初の音節 “sun” に強勢が置かれる傾向があります。
- “SUN-rise” のように、最初の音節 “sun” に強勢が置かれる傾向があります。
アメリカ英語とイギリス英語の違い:
- 大きな違いはありませんが、一部話者の発音により “raɪz” 部分が微妙に変化することがあります。
- 大きな違いはありませんが、一部話者の発音により “raɪz” 部分が微妙に変化することがあります。
よくある間違い:
- “sun” の母音を /æ/ で発音してしまうなど。正しくは /ʌ/ です。
- スペルミス: “sunrise” を “sunrice” のように書き間違えることがあります。
- 同音異義語との混同: 特に似た単語はありませんが、「sunset」と混同してしまう学習者はまれにいます。意味が正反対なので注意しましょう。
- 試験対策(TOEIC・英検など):
- 論説や自然に関する記述で日の出・日の入りを表す時に出題されることがあります。
- セクションによっては天気予報の文章や観光案内の文脈で見かけることもあります。
- 論説や自然に関する記述で日の出・日の入りを表す時に出題されることがあります。
- 「sun」(太陽)+「rise」(昇る)で、“太陽が昇る瞬間” とイメージしやすい構成になっています。
- 「日の出の光が差し込む様子」を頭に描きながら、同時に “SUN-rise” と声に出して覚えると記憶に残りやすいです。
- スペリングの際には、「sun」と「rise」がくっついているが間に ‘r’ がもう一回出てこないように意識すると良いでしょう。
- 朝日を浴びて活動開始するイメージで、英単語の意味を思い出しやすくなります。
- dangerous (形容詞)
- dangerously (副詞)
- danger (名詞): 危険
- endanger (動詞): 危険にさらす
- endangered (形容詞): 絶滅の危機にひんした(※動物や植物などに対して使われることが多い)
- B2(中上級): 日常会話で「危険」のニュアンスをより具体的に表す場面で使われるため、中上級レベルと考えられます。
- danger(危険) + -ous(形容詞化する接尾辞) → dangerous
- dangerous + -ly(副詞化する接尾辞)→ dangerously
- danger (名詞)
- dangerous (形容詞)
- dangerously (副詞)
- endanger (動詞)
- endangerment (名詞)
- dangerously close to the edge(崖っぷちに危険なまでに近い)
- dangerously high speed(危険なほどに速い速度)
- dangerously low levels(危険なほど低い水準)
- dangerously unstable(危険なほど不安定な)
- dangerously ill(危篤状態の)
- dangerously exposed(危険にさらされている)
- dangerously toxic(危険なほど有毒な)
- dangerously high blood pressure(危険なほど高い血圧)
- dangerously unpredictable(危険なほど予測不能な)
- dangerously addicted(危険なほど中毒になっている)
- 「danger」はラテン語の“dominus”(主人、権威)に由来する中世フランス語“dangier”から来ています。「権威のある人の制裁下にある状態」が広がって“リスクがある”“危険”の意味になりました。
- そこから英語で「danger」となり、形容詞「dangerous」が生まれ、さらに副詞「dangerously」が派生しました。
- 「dangerously」は“深刻な危険”を示すため、比較的強いニュアンスがあります。
- 口語・文章どちらでも使えますが、強調度が高く、聞く人には深刻さや緊迫感を与えます。
- 注意深く使わないと、必要以上に強い表現になってしまう場合があります。
- 「dangerously」は副詞なので、主に動詞や形容詞、さらには他の副詞を修飾します。
- 例)She drove dangerously. (彼女は危険なほどに運転した)
- 例)It was dangerously close to the edge. (それは崖っぷちに危険なほど近かった)
- 例)She drove dangerously. (彼女は危険なほどに運転した)
- “drive dangerously”:「危険な運転をする」
- “play dangerously with fire”:「(比喩的にも)火遊びをする/危険な冒険をする」
- 一般的にはニュートラルですが、内容が深刻な場合が多いため、ニュース記事やレポートでもよく見られます。
- カジュアル会話でも使われますが、「すごく危険」という強いニュアンスになるので、内容上慎重に使われます。
“He was driving dangerously on the highway yesterday.”
(彼は昨日、高速道路で危険なほどの運転をしていたよ。)“That knife is dangerously sharp. Be careful!”
(そのナイフ、危険なほどよく切れるよ。気をつけて!)“She stood dangerously close to the edge of the cliff.”
(彼女は崖っぷちに危険なほど近づいて立っていた。)“Our finances are dangerously low; we need to cut costs immediately.”
(財務状況が危険なほど悪化しているので、すぐに経費を削減する必要があります。)“This new policy could dangerously affect our market share.”
(この新しい方針は、私たちの市場シェアに深刻な影響を及ぼしかねません。)“We are dangerously behind schedule with this project.”
(このプロジェクトはスケジュールに危険なほどの遅れが生じています。)“Levels of pollution in the city have risen dangerously, according to the latest study.”
(最新の研究によると、その都市の汚染レベルは危険なほど上昇している。)“Glaciers are melting dangerously fast due to climate change.”
(気候変動の影響で、氷河が危険なくらいの速さで溶けている。)“The virus mutates dangerously, complicating vaccine development.”
(そのウイルスは危険な形で変異を起こし、ワクチン開発を複雑にしている。)- hazardously(危険なほどに)
- 「危険」と強く結びつく表現。やや専門的・技術的なニュアンスがある。
- 「危険」と強く結びつく表現。やや専門的・技術的なニュアンスがある。
- perilously(非常に危険なほどに)
- 「命に関わるような危険さ」を強調する場合に多い。文学的表現にも現れる。
- 「命に関わるような危険さ」を強調する場合に多い。文学的表現にも現れる。
- unsafely(安全でないやり方で)
- 場合によっては「不注意」のニュアンスが強い。
- 場合によっては「不注意」のニュアンスが強い。
- riskily(リスクを伴う形で)
- カジュアルに「リスキーに」とも訳せる。
- カジュアルに「リスキーに」とも訳せる。
- safely: 安全に
- 「危険」とは正反対の意味で、“安全なやり方”を示す。
- dangerously: /ˈdeɪn.dʒər.əs.li/
- 最初の音節 “dan-” にアクセントがあります(“dayn”のように音が伸びるイメージ)。
- アメリカ英語では /ˈdeɪn.dʒɚ.əs.li/ のように “r” が明確に発音されます。
- イギリス英語では /ˈdeɪn.dʒər.əs.li/ と “r” はやや弱めに発音されます。
- “dangerous” と同じアクセントを保ちつつ、最後まで尻切れにならないように “‐ly” をはっきり発音する点に注意。
- 品詞の混同
- 「dangerous(形容詞)」と間違えて「dangerously」を形容詞だと思いがちですが、実際は副詞です。
- 「dangerous(形容詞)」と間違えて「dangerously」を形容詞だと思いがちですが、実際は副詞です。
- つづりの間違い
- “dangerous” に “-ly” を加えるときに “u” を抜かして “dangerosly” と書いてしまうミスに注意。
- “dangerous” に “-ly” を加えるときに “u” を抜かして “dangerosly” と書いてしまうミスに注意。
- 試験での扱い
- TOEICや英検などでも副詞のつづりや運用が問われることがあるので、名詞・形容詞・副詞の変化を意識して覚えるとよいです。
- 「danger + ous + ly」で「危険 + 形容詞化 + 副詞化」の流れとして覚えるとわかりやすいです。
- 動作や状態の危険度を強調したいときに「dangerously」を使うとイメージしやすいでしょう。
- “anger”が含まれているため、強い危機感を伴う単語というイメージを持つと印象に残りやすいかもしれません。
- hand: 「手」
- ball: 「ボール」
- “handball court” (ハンドボールコート)
- “handball player” (ハンドボール選手)
- “team handball” (チームスポーツとしてのハンドボール)
- “American handball” (アメリカ式の壁打ちハンドボール)
- play handball → ハンドボールをする
- handball match → ハンドボールの試合
- professional handball → プロのハンドボール(リーグ・競技)
- indoor handball → 室内ハンドボール
- handball court → ハンドボールコート
- handball team → ハンドボールチーム
- handball federation → ハンドボール連盟
- handball skills → ハンドボールの技術
- European handball → ヨーロッパで主流のハンドボール
- beach handball → ビーチで行われるハンドボール
- チームスポーツとしてのハンドボールを指す場合と、壁打ち形式のハンドボールを指す場合があります。
- 競技人口の多いヨーロッパで「handball」と言えば、ほぼ“チームハンドボール”を指しますが、アメリカでは壁打ち形式のハンドボールもポピュラーです。
- 口語・文章共に比較的カジュアルに使われる単語です。
- 可算名詞: 一般的には「(1試合の) ハンドボール」「いくつものハンドボール(競技)」と数える場合は可算扱いが可能です。ただし「ハンドボールという競技全般」を指す文脈では不可算的に扱うこともあります。
- 構文例: “I play handball.” / “He is a handball player.” のように、主語 + play + handball で「ハンドボールをする」という表現が一般的です。
- イディオム的表現はあまり多くありませんが、「handball it」などはあまり使われません。
- “I joined the school’s handball club last week.”
(先週、学校のハンドボール部に入ったんだ。) - “Let’s go watch a handball match this weekend.”
(今週末にハンドボールの試合を見に行こうよ。) - “Have you ever played handball before?”
(今までにハンドボールをしたことある?) - “Our company is sponsoring a local handball tournament.”
(当社は地元のハンドボールの大会をスポンサーしています。) - “We organized a friendly handball match with our clients.”
(クライアントとの親善ハンドボールの試合を企画しました。) - “The handball team’s performance has significantly boosted our brand visibility.”
(そのハンドボールチームの活躍によって、私たちのブランドの認知度が大いに高まりました。) - “According to recent studies, handball training improves both aerobic and anaerobic fitness levels.”
(最近の研究によると、ハンドボールのトレーニングは有酸素能力と無酸素能力の両面で改善効果がある。) - “The historical evolution of handball reflects its regional adaptations across Europe and North America.”
(ハンドボールの歴史的発展は、ヨーロッパと北米での地域的適応を反映している。) - “Advanced biomechanical analysis of handball throws provides insights into injury prevention.”
(ハンドボールのスローを高度な生体力学的に分析することで、ケガの予防に関する知見が得られる。) - “team handball” → (チームスポーツとしての) ハンドボール
- “European handball” → 欧州式のハンドボール
- アメリカ英語: /ˈhændˌbɔːl/ または /ˈhændˌbɑːl/
- イギリス英語: /ˈhænd.bɔːl/
- “HAND” の部分に強勢があり、次の “ball” はやや弱めになります(ˈhænd-bɔːl)。
- “hand” を「ハンド」でなく「ハン(d)」と曖昧に発音しがち。 “catchball” と混同したりする例もあるので注意。
- スペルミス: × “handbol”, × “handboll” など、特に“ball”部分の綴りに注意してください。
- 同音異義語との混同: 特にはありませんが、“handle”などの類似スペリングには注意。
- 試験対策: TOEICや英検などではスポーツ関連の読解問題・長文やリスニングで出題される可能性があります。単語自体は難しくありませんが、競技名称に関する問題で扱われることがあります。
- 「手 (hand) で扱うボール (ball)」という、そのままの合成語なので覚えやすい単語です。
- スペリングのポイントとしては「hand + ball」がくっついた形のため、間に余計な文字を入れないようにすると良いでしょう。
- 「手」と「ボール」というわかりやすいイメージから想像すると記憶に残りやすくなります。
- 例: one league (1つのリーグ)、two leagues (2つのリーグ)
- 動詞形 (やや稀): to league (同盟する、団結する)
- 例: “They decided to league together against the invading army.”
- 例: “They decided to league together against the invading army.”
- B1(中級): 日常的なトピックでの会話や情報収集ができるレベル。スポーツや国際関係の話題でよく登場する単語です。
- 接頭語や接尾語はなく、語幹 “league” のみで構成されています。
- 中世フランス語 (ligue) が起源。
- 同盟(政治的・軍事的): 複数の国や勢力が共同目的のために協力し合うこと。
- 連盟・リーグ(スポーツ・競技): スポーツチームやクラブが集まり、定期的に試合などを行う組織体。
- 距離の単位(古風): 歴史的に「リーグ」は約3マイルやさまざまな長さを指したが、現代ではあまり用いられない。
- “join a league” – リーグに参加する
- “football league” – サッカーリーグ
- “in the same league” – 同じレベル/同格
- “major league” – メジャーリーグ(大規模なリーグ)
- “minor league” – マイナーリーグ
- “out of one’s league” – (比喩的に)力が及ばない、分不相応
- “league championship” – リーグ選手権
- “league table” – リーグ順位表(結果を一覧にした表)
- “breakaway league” – 離脱して作られた新リーグ
- “form a league” – リーグを結成する
- 中世フランス語 “ligue” が語源で、更にラテン語 “ligare”(結びつける)が由来とされています。
- 歴史的には、国同士が協力し合う「同盟」の意味が強く、近代以降スポーツにも適用されました。
- 「league」は「協力」や「連携」のニュアンスがあり、特にスポーツでは競争しつつも同じ組織・枠組みに所属している協同性を強調します。
- 口語・文章どちらでも使用可能。スポーツ以外で同盟を指すときは、ややフォーマルな響きを帯びます。
- 可算名詞として使われるため、冠詞 (a, the) や数 (one league, two leagues) に注意して使います。
- to league (動詞) はあまり日常的ではありませんが、“league with 〜” で「〜と同盟を結ぶ」という表現が可能です。
- “be in a league of one’s own” (別格である)
- “be out of someone’s league” (相手が自分には高嶺の花である、力の差がある)
- 「スポーツリーグ」に関する話題であればカジュアル。
- 「国家間の同盟」について述べる文脈ではフォーマル。
“I’m really excited because my favorite team just joined a new league!”
- 「私の大好きなチームが新しいリーグに加わったから、すごくワクワクしてるんだ!」
“He’s so good at basketball that he’s in a league of his own.”
- 「彼はバスケがとても上手くて、まさに別次元のプレーをしているよ。」
“I wonder if our local football league will have a tournament this year.”
- 「今年、地元のサッカーリーグで大会があるのかな?」
“Our company formed a league with smaller startups to share resources.”
- 「私たちの会社は、リソースを共有するために小規模企業との連盟を結成しました。」
“The new trade league aims to reduce taxes across member states.”
- 「新しい貿易連盟は、加盟国間の税金を減らすことを目指しています。」
“They decided to dissolve the league due to ongoing financial issues.”
- 「継続的な財政問題により、その連盟は解散を決定しました。」
“According to historical documents, the nations in the league pledged mutual defense.”
- 「歴史的な文書によると、その同盟に参加していた国々は相互防衛を誓約していました。」
“Researchers analyzed the impact of international leagues on global politics.”
- 「研究者たちは国際同盟が世界の政治に与える影響を分析しました。」
“The Sports Science journal published a comparative study of players’ performance in various leagues.”
- 「スポーツ科学のジャーナルは、さまざまなリーグにおける選手のパフォーマンスを比較した研究を発表しました。」
- alliance (同盟) – 国や組織が協力するための公式な関係
- association (協会) – 共通の目的のために結成された団体
- union (組合 / 同盟) – 労働組合や国家の連合など幅広く使用
- coalition (連立 / 連合) – 政党や組織が協力する形
- federation (連邦 / 連盟) – 中央組織に一定の権限がある連合
- rivalry (ライバル関係) – 協力するよりも競争しあうことを強調
- opposition (反対) – 協力ではなく対立する立場
- アメリカ英語 (AE): [リーグ] 1音節。
- イギリス英語 (BE): [リーグ] ほぼ同じ発音で大差はありません。
- スペルミス: 「league」を「leage」や「leauge」と書いてしまう。
- 「-ue」の順番を意識して覚えると良いです。
- 「-ue」の順番を意識して覚えると良いです。
- 同音異義語との混同: 基本的に同音異義語はありませんが、「league」と「leak (漏れる)」を混同しないように注意してください。
- 試験対策: TOEICや英検では、スポーツや同盟関係を説明する文章中などで読解問題に出されることがあります。意味と用法をしっかり把握しておきましょう。
- “ea” の組み合わせ: 「peace」「leave」「league」のように“e + a”が「イー」の音になる単語は少なくありません。
- 語末 “-gue”: “dialogue”「対話」、 “intrigue”「陰謀」なども同じ“-gue”で終わる英単語があるので、あわせて覚えるとスペルミスを防げます。
- イメージ連想: 「同じゴール(GOAL)に向かって“結ばれる (ligare)”」という元のラテン語から、みんなが集まって協力するイメージを持つと覚えやすいでしょう。
(タップまたはEnterキー)
彼は生涯にわたってそのチームのファンです。
彼は生涯にわたってそのチームのファンです。
彼は生涯にわたってそのチームのファンです。
解説
彼は生涯にわたってそのチームのファンです。
lifelong
1. 基本情報と概要
単語: lifelong
品詞: 形容詞 (Adjective)
意味(英語): “lasting for the whole of a person’s life”
意味(日本語): 「生涯にわたる」「一生続く」
「lifelong」は「生涯を通じてずっと続く」というニュアンスを持つ形容詞です。たとえば「lifelong friend」で「一生の友」「生涯の友」というように使われます。人生を丸ごと通して続くものを強調するときに便利な単語です。
CEFR レベルの目安: B2(中上級)
活用形
形容詞なので直接的な活用形はありませんが、比較級や最上級は通常作りません(“more lifelong” や “most lifelong” は通常使用しません)。
他の品詞になった時の例
2. 語構成と詳細な意味
語構成
それぞれの単語が組み合わさって「人生全体が長く続く」という意味を持ちます。
関連語や派生語
よく使われるコロケーション(10個)
3. 語源とニュアンス
語源
ニュアンス
「人生を通じてずっと続く」という強い継続性を強調します。フォーマル/インフォーマルどちらでも使いやすい単語ですが、「一生の友達」「一生の夢」のように、特別な価値や深いつながりを語るシーンでよく用いられます。
4. 文法的な特徴と構文
一般的な構文・使用例
形容詞なので、名詞を修飾する形で使うのが基本です。可算・不可算や他動詞・自動詞のように特別な区別はありません。
5. 実例と例文
(1) 日常会話での例文
(2) ビジネスでの例文
(3) 学術的な文脈での例文
6. 類義語・反意語と比較
類義語
反意語
7. 発音とアクセントの特徴
強勢(アクセント)は「life」の部分(最初の音節)に置かれます。
よくある間違いとしては「ライフ」と「ロング」の間を区切ってしまったり、life long
と2単語で書いてしまうことが挙げられます。
8. 学習上の注意点・よくある間違い
資格試験やTOEICなどでも、読解に出ることがありますが、それほど頻繁に出題される語ではありません。文脈から正しい意味を推測しやすい単語です。
9. 記憶に残るヒントやイメージ
ぜひ “lifelong friend” や “lifelong passion” などのフレーズを声に出して繰り返し練習して、自分の英語表現の中に取り入れてみてください。
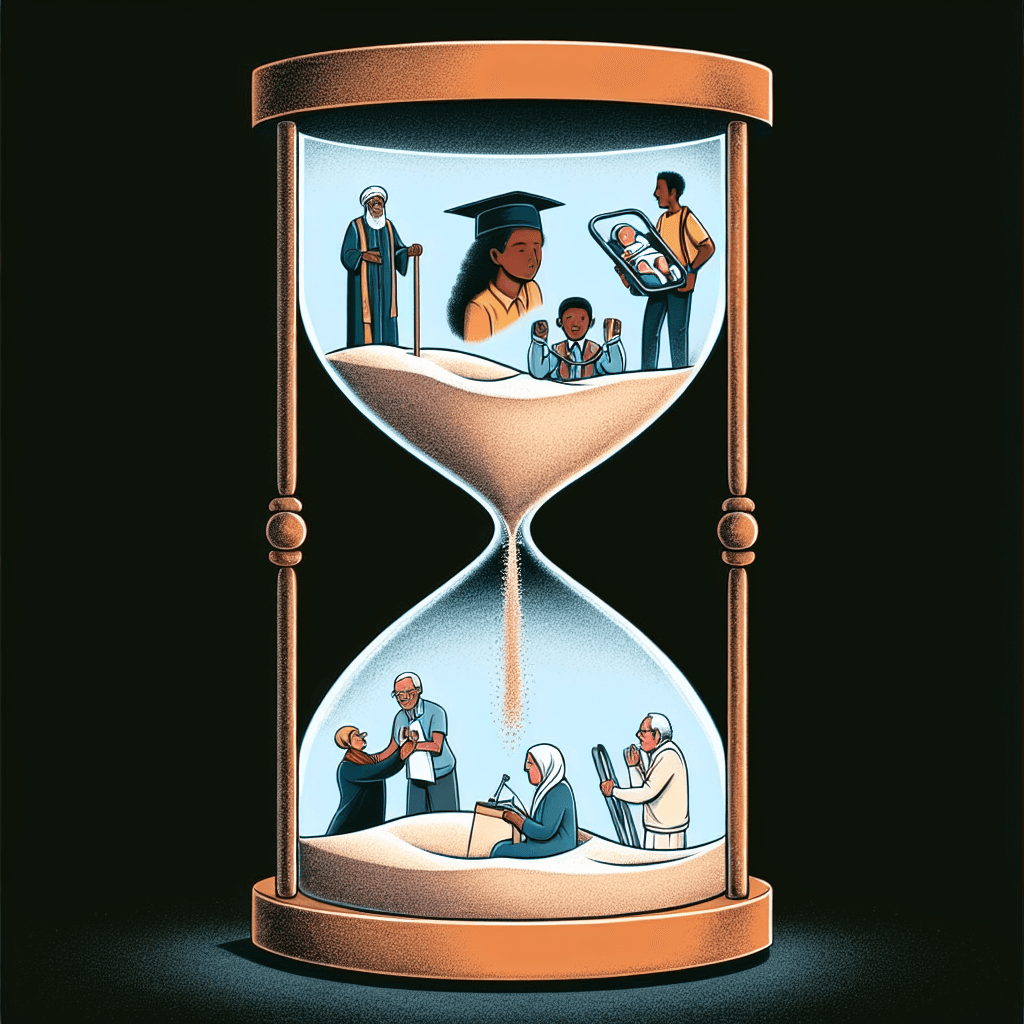
終生の,生涯の
象は大きいです。
象は大きいです。
解説
象は大きいです。
massive
以下では英単語「massive」について、できるだけ詳しく解説します。
1. 基本情報と概要
意味 (英語・日本語)
品詞
活用形
他の品詞への変化
CEFR レベル目安
2. 語構成と詳細な意味
接頭語・接尾語・語幹
他の単語との関連性(派生語)
よく使われるコロケーションや関連フレーズ(10個)
3. 語源とニュアンス
語源
微妙なニュアンスや感情的な響き
4. 文法的な特徴と構文
一般的な構文
イディオム的用法
フォーマル/カジュアル
文法上のポイント
5. 実例と例文
日常会話(カジュアル)の例文
ビジネスでの例文
学術的(アカデミック)な文脈の例文
6. 類義語・反意語と比較
類義語(Synonyms)
これらはすべて「とても大きい」という意味ですが、
反意語(Antonyms)
7. 発音とアクセントの特徴
8. 学習上の注意点・よくある間違い
9. 記憶に残るヒントやイメージ
以上が形容詞「massive」の詳細な解説です。日常会話からビジネス、学術場面まで幅広く活用できる単語なので、場面に応じて使い分けてみてください。

大きくて重い,どっしりした;
大規模な , 膨大な
(容ぼう,特に頭が)がっちりした
(精神などが)しっかりした,堂々とした
(投薬量が)定量以上の
(タップまたはEnterキー)
旅行する前に、パスポートを更新する必要があります。
旅行する前に、パスポートを更新する必要があります。
旅行する前に、パスポートを更新する必要があります。
解説
旅行する前に、パスポートを更新する必要があります。
passport
名詞 “passport” の詳細解説
1. 基本情報と概要
英単語: passport
品詞: 名詞 (countable noun)
活用形: 単数形: passport / 複数形: passports
意味(英語 / 日本語)
「海外旅行をするために必ず必要となる身分証明書です。飛行機の搭乗や入国審査などの手続きで提示するので、旅をする人にとってとても重要なものです。」
他の品詞になった場合の例
“passport” は名詞なので、他の品詞への変化は一般的にはあまり見られません。ただし、比喩的表現や複合語として他の形に連結する場合はあります(例えば “passport photo” などは形容詞的に使われています)。
CEFR レベルの目安
2. 語構成と詳細な意味
語構成
関連語・派生語
コロケーション(共起表現)10選
3. 語源とニュアンス
語源
ニュアンス・使用時の注意
4. 文法的な特徴と構文
イディオムや関連表現
5. 実例と例文
日常会話での例文
ビジネスシーンでの例文
学術的・フォーマルな文脈での例文
6. 類義語・反意語と比較
類義語
“passport” は公的に発行され、海外での身分証として認められる点が最大の特徴です。
反意語
7. 発音とアクセントの特徴
8. 学習上の注意点・よくある間違い
9. 記憶に残るヒントやイメージ
以上が、名詞 “passport” に関する詳細な解説です。旅行や留学のシーンだけでなく、公的書類としても重要な単語なので、しっかり覚えておきましょう。

旅券,パスポート
《単数形で》(…への)手段,便法《+to+名》
(タップまたはEnterキー)
彼女は乳房にしこりを感じ、すぐに医者に診てもらいました。
彼女は乳房にしこりを感じ、すぐに医者に診てもらいました。
彼女は乳房にしこりを感じ、すぐに医者に診てもらいました。
解説
彼女は乳房にしこりを感じ、すぐに医者に診てもらいました。
breast
1. 基本情報と概要
単語: breast
品詞: 名詞 (noun)
CEFRレベル目安: B2(中上級)
意味(英語): Refers to the chest area on the front of the human body (especially of a woman), or in general (for both men and women) the front part of the body between the neck and abdomen; it can also refer to the front part of a bird’s body or a piece of poultry meat.
意味(日本語): 人の胸部(特に女性の乳房)を指し、鳥の場合は胸肉を指すこともあります。女性の身体的特徴を表すときや、「チキンの胸肉」など料理の文脈でもよく使われる単語です。「breast」は直接的に体の一部としての乳房を意味するため、使う場面や文脈には注意する必要があります。
活用形・関連形
2. 語構成と詳細な意味
語構成
詳細な意味
よく使われるコロケーション(10個)
3. 語源とニュアンス
語源
ニュアンス
4. 文法的な特徴と構文
構文例
5. 実例と例文
日常会話での例文(3つ)
ビジネスでの例文(3つ)
学術的/医療的な文脈での例文(3つ)
6. 類義語・反意語と比較
類義語
反意語
7. 発音とアクセントの特徴
8. 学習上の注意点・よくある間違い
9. 記憶に残るヒントやイメージ
以上が名詞「breast」の詳細な解説です。女性の身体に関わる単語だけに、日常会話での使い方や文脈には配慮が必要ですが、医療や料理をはじめとする多彩なシーンで頻出する重要単語です。
(タップまたはEnterキー)
この出来事の歴史的な意義はどれだけ誇張してもしすぎることはありません。
この出来事の歴史的な意義はどれだけ誇張してもしすぎることはありません。
この出来事の歴史的な意義はどれだけ誇張してもしすぎることはありません。
解説
この出来事の歴史的な意義はどれだけ誇張してもしすぎることはありません。
historical
1. 基本情報と概要
単語: historical
品詞: 形容詞 (adjective)
意味 (英語): relating to history; concerning past events
意味 (日本語): 歴史に関する、過去の出来事に関する
「historical」は、何かが「歴史上の事柄、過去に実際にあったできごとや、歴史そのもの」に関連しているというニュアンスで使われます。たとえば「historical event」(歴史的な出来事)や「historical figure」(歴史上の人物)のように、過去に存在していた事柄を指すときに使われます。
活用形
この単語は形容詞なので、動詞のように時制による活用はありません。
他の品詞になったときの例
CEFRレベル目安
2. 語構成と詳細な意味
「historical」は、接尾語 -ical を “history” に付けて「歴史に関する」という意味を作り出しています。
関連語や派生語
“historic” と “historical” の違い
よく使われるコロケーション(関連フレーズ10選)
3. 語源とニュアンス
使用上のニュアンスや注意点
4. 文法的な特徴と構文
一般的な構文・イディオム
これらは論文やレポートなどで見かけるフォーマルな用法です。
5. 実例と例文
日常会話 (3例)
ビジネス (3例)
学術的な文脈 (3例)
6. 類義語・反意語と比較
類義語
“historical” は「歴史上に存在した・関係する」という意味にとどまるのに対し、 “historic” は「歴史的に重要な」というニュアンスであり、そこに大きな違いがあります。
反意語
7. 発音とアクセントの特徴
8. 学習上の注意点・よくある間違い
9. 記憶に残るヒントやイメージ
「historical」は、過去の事柄を指す際の基本的な形容詞として非常によく使われる単語です。ぜひ “historic” と使い分けて、正しい文脈で活用してみてください。

歴史の,史学の
史実の基づく,歴史上の
(タップまたはEnterキー)
同地区は毎週ゴミの収集を行っていた。
同地区は毎週ゴミの収集を行っていた。
同地区は毎週ゴミの収集を行っていた。
解説
同地区は毎週ゴミの収集を行っていた。
refuse
1. 基本情報と概要
単語: refuse
品詞: 名詞 (不可算名詞)
活用形: 名詞のため基本的に変化(複数形など)はありません。ただし文脈によってはまれに“refuses”と見かけることもありますが、通常は不可算として使われます。
(※同じスペルで動詞の「to refuse(断る)」がありますが、アクセントや意味が異なるため注意が必要です。)
意味 (英語・日本語)
「refuse」は「ゴミや廃棄物」の意味で、一般的に「捨てられるもの」や「不要物」というニュアンスで使われる単語です。日常会話ではあまり一般的でなく、文書や少し硬い場面で目にすることが多いでしょう。
CEFRレベルの目安
2. 語構成と詳細な意味
語構成
“refuse”という単語は、フランス語の“refuser”(動詞「断る」)を経由して英語に入ったと考えられています。もともとre-(再び)+ fuser(注ぐ/resue)などの形に由来するとされますが、動詞形“to refuse”とはアクセント・品詞が異なります。名詞形の場合、もはや接頭語・接尾語で明確に区切れるわけではなく、語幹全体として「廃棄物」を指す意味になっています。
代表的な派生語・関連語
よく使われるコロケーション(共起表現)や関連フレーズ(10個)
3. 語源とニュアンス
語源
使用のニュアンス
4. 文法的な特徴と構文
5. 実例と例文
日常会話での例文(3つ)
※日常会話では“trash” や “garbage”に置き換える方が自然です。
ビジネスでの例文(3つ)
学術的・公的な文脈での例文(3つ)
6. 類義語・反意語と比較
類義語(Synonyms)
→ “refuse”はそれらに比べてやや公的・形式的なニュアンスが強い。
反意語(Antonyms)
7. 発音とアクセントの特徴
よくある発音ミス
8. 学習上の注意点・よくある間違い
9. 記憶に残るヒントやイメージ
以上が名詞「refuse」の詳細な解説です。動詞「to refuse」との発音・意味の違いに注意しつつ、環境問題や廃棄物処理の話題にもよく登場するため、語彙として押さえておくと便利です。

廃物,くず,ごみ
(タップまたはEnterキー)
私は日の出を見るために早起きしました。
私は日の出を見るために早起きしました。
私は日の出を見るために早起きしました。
解説
私は日の出を見るために早起きしました。
sunrise
1. 基本情報と概要
sunrise(名詞)
「sunrise」は、朝に太陽が昇る瞬間や、その時刻そのものを指す単語です。美しい景色を楽しむときや、1日の始まりを強調するときに使われます。とてもポジティブで清々しいニュアンスがあり、日常会話でもよく登場します。
2. 語構成と詳細な意味
3. 語源とニュアンス
4. 文法的な特徴と構文
5. 実例と例文
(A) 日常会話での例文
(B) ビジネスシーンでの例文
(C) 学術的 / 公的な文脈での例文
6. 類義語・反意語と比較
7. 発音とアクセントの特徴
8. 学習上の注意点・よくある間違い
9. 記憶に残るヒントやイメージ
以上が、名詞 「sunrise」 の詳細解説です。日の出の美しい瞬間をイメージしつつ、日常やビジネスシーンでもぜひ使ってみてください。

日の出
日の出の時刻
(タップまたはEnterキー)
彼は高速道路で危険なほど速く運転した。
彼は高速道路で危険なほど速く運転した。
彼は高速道路で危険なほど速く運転した。
解説
彼は高速道路で危険なほど速く運転した。
dangerously
1. 基本情報と概要
単語: dangerously
品詞: 副詞 (adverb) ※「dangerously」は形容詞「dangerous」の副詞形です。
意味(英語): in a way that is likely to cause harm or injury
意味(日本語): 危害や損害を引き起こしかねない方法・状態で
「dangerously」は、何かが“危険なほどに”という意味を強調する時に使われます。たとえば、「スピードが危険なほどに速い」「状況が危険なまでに不安定だ」のように、予期せぬ不測の事態やリスクを強調するときに用いられます。
活用形
※「dangerous(形容詞)」 → 「dangerously(副詞)」のように、-lyをつけることで「形容詞」→「副詞」に変化します。
他の品詞例
CEFRレベル(目安)
2. 語構成と詳細な意味
語構成
関連する派生語や類縁語
よく使われるコロケーション(共起表現)10選
3. 語源とニュアンス
語源
ニュアンスや使用上の注意
4. 文法的な特徴と構文
一般的な構文・イディオム
フォーマルかカジュアルか
5. 実例と例文
以下、日常会話・ビジネス・学術的文脈ごとに3例ずつ挙げます。
日常会話
ビジネス
学術的な文脈
6. 類義語・反意語と比較
類義語
反意語
7. 発音とアクセントの特徴
発音記号(IPA)
アクセントの位置
アメリカ英語とイギリス英語の違い
よくある発音の間違い
8. 学習上の注意点・よくある間違い
9. 記憶に残るヒントやイメージ
以上が「dangerously」の詳細解説です。「危険なまでに」を強調する副詞ですので、しっかり文脈に合わせて使い分けましょう。

危険なほど;危うく
(タップまたはEnterキー)
私は友達とハンドボールをするのが楽しいです。
私は友達とハンドボールをするのが楽しいです。
私は友達とハンドボールをするのが楽しいです。
解説
私は友達とハンドボールをするのが楽しいです。
handball
1. 基本情報と概要
英単語: handball
品詞: 名詞 (n.)
意味(英語)
A sport in which players use their hands to pass a ball and attempt to score goals.
意味(日本語)
ボールを手で扱ってゴールに入れることを目的とするスポーツ(チームスポーツのハンドボール、または壁打ち競技のハンドボールなど)。
「手を使ってプレーするスポーツで、チームごとにゴールを奪い合う競技です。主に体育館などでプレーされることが多く、テンポの速い攻防が特徴です。」
活用形
名詞なので基本的に “handball” の形のみで、複数形は “handballs” となります。
他の品詞には基本的になりませんが、「handball」を動詞的に「ハンドボールのようにプレーする」と表現する口語用法はほぼありません。
CEFRレベルの目安: B1(中級)
日常会話でスポーツを話題にできるレベル。スポーツ名としてはA2程度でも使う機会がありますが、詳しく説明するとなるとB1レベル程度の表現力が求められます。
2. 語構成と詳細な意味
語構成
この2つの単語が合わさった合成語 (compound word) です。
関連語や派生語
よく使われるコロケーション(10個)
3. 語源とニュアンス
語源
“hand” (手) + “ball” (ボール) という直接的な組み合わせから生まれた単語です。19世紀頃に、手を使って行う球技を総称して“handball”と呼んだのが始まりとされます。ヨーロッパでのチームスポーツとしても発展し、アメリカでは壁打ち版のハンドボールが親しまれています。
ニュアンス・使用上の注意
4. 文法的な特徴と構文
5. 実例と例文
日常会話での例文
ビジネスシーンでの例文
学術・フォーマルな文脈での例文
6. 類義語・反意語と比較
類義語 (Synonyms)
※厳密には同一競技の呼称の違いなので完全な類義語というより別名に近いです。
反意語 (Antonyms)
スポーツ名のため直接的な反意語はありませんが、「football (サッカー)」「basketball」など、手を使わない球技を対比として挙げることはできます。
7. 発音とアクセントの特徴
発音記号
アクセントの位置
よくある発音のミス
8. 学習上の注意点・よくある間違い
9. 記憶に残るヒントやイメージ
以上が「handball」の詳細な解説です。気軽に使えるスポーツ名ですが、チームスポーツなのか壁打ちのものなのか、文脈によって指し示すものが異なる点に注意するとよいでしょう。

〈U〉ハンドボール
〈C〉ハンドボール用のボール
(タップまたはEnterキー)
彼女は地元のサッカーリーグでプレーしています。
彼女は地元のサッカーリーグでプレーしています。
彼女は地元のサッカーリーグでプレーしています。
解説
彼女は地元のサッカーリーグでプレーしています。
league
名詞 “league” の詳細解説
1. 基本情報と概要
単語: league
品詞: 名詞 (可算名詞)
日本語の意味: 「同盟」「連盟」「リーグ」など
英語での簡潔な意味:
“league” means a group of individuals, teams, or nations that have joined together for a common purpose (e.g., a sports league or an alliance).
日本語でのやさしい説明:
「league」は、複数のチームや国、または個人が集まり、何かをいっしょに行うための“連盟”や“同盟”を指す言葉です。スポーツチームが集まる「リーグ戦」や国同士で結ぶ「同盟関係」など、共通の目的や利害があるグループを表します。普段の会話でも、特にスポーツの文脈でよく聞かれます。
活用形: 可算名詞なので、単数 “league” / 複数形 “leagues”
他の品詞形:
CEFRレベルの目安: B1(中級)
2. 語構成と詳細な意味
語構成:
詳細な意味:
関連フレーズ・コロケーション 10選
3. 語源とニュアンス
語源:
ニュアンス:
4. 文法的な特徴と構文
文法上のポイント:
一般的な構文・イディオム:
フォーマル / カジュアル:
5. 実例と例文
日常会話での例文 (3つ)
ビジネスシーンでの例文 (3つ)
学術的・公式文脈での例文 (3つ)
6. 類義語・反意語と比較
類義語 (Synonyms)
※「league」はスポーツ文脈では「リーグ」、政治・軍事文脈では「同盟」に近く、他の単語は固有の文脈に応じて使われます。
反意語 (Antonyms)
7. 発音とアクセントの特徴
発音記号 (IPA): /liːɡ/
アクセント: 1音節の単語なので特にアクセント移動はありません。
よくある間違い: “league” を [liːg] と発音せず、 /leɪɡ/ や /liːdʒ/ のように間違える場合があります。
8. 学習上の注意点・よくある間違い
9. 記憶に残るヒントやイメージ
以上が名詞 “league” の詳細解説です。スポーツから国際関係まで幅広く使われる単語なので、文脈に合わせて使い分けられるよう練習してみてください。

競技連盟,リーグ
(国家・人々・組織などの)連盟,同盟
リーグ(昔の距離の単位;約3マイル(5キロメートル))
loading!!

CEFR-J B1 - 中級英単語

CEFR-JのB1レベル(中級レベル)の英単語を覚えられる問題集です。
英語学習者必見!東京外国語大学が開発した最強の頻出英単語・英文法リスト!!【CEFR-J Wordlist, CEFR-J Grammar Profile】
外部リンク
キー操作
最初の問題を選択する:
Ctrl + Enter
解説を見る:Ctrl + G
フィードバックを閉じる:Esc
問題選択時
解答する:Enter
選択肢を選ぶ:↓ or ↑
問題の読み上げ:Ctrl + K
ヒントを見る: Ctrl + M
スキップする: Ctrl + Y





