ビジネス英単語(BSL) / 英訳 / 4択問題 - 未解答
日本語に対応する正しい英単語を、4つの選択肢から答える問題です。
英単語の意味を覚えるのに役立ちます。
- 「trait」は不可算名詞ではなく可算名詞で単数形・複数形が使えますが、実質的に「trait」の複数形「traits」もよく使われます。
- この単語自体に動詞形や形容詞形・副詞形はありません。
- 直接的な変化形はありませんが、類似の意味をもつ語として、形容詞では「trait-like」というように複合語として使われる場合があります(例: “trait-like behaviors”)。
- B2レベル: 日常会話にはあまり出ないものの、学術的なテキストやビジネス文書でも使われる比較的発展的な単語です。
- 英語の「trait」は、フランス語から取り入れられたという背景があり、接頭語・接尾語などで分解できる英語的構成要素はありません。
- 「attribute」(属性)
- 「characteristic」(特徴)
- 「feature」(特徴)
- 「quality」(品質・特質)
- personality trait(人格的特徴)
- character trait(性格的特徴)
- genetic trait(遺伝的特性)
- dominant trait(優性特徴)
- shared trait(共通の特徴)
- physical trait(身体的特性)
- negative trait(好ましくない特徴)
- positive trait(好ましい特徴)
- unique trait(独特の特徴)
- hereditary trait(遺伝的に受け継がれた特性)
- 「trait」という単語はフランス語由来で、もともとは「線を描くこと」や「引くこと」などを意味していました。ラテン語“tractus”(引く、引っ張る)を語源とします。「一本の線を引いて際立たせる」というイメージが派生し、「その人や物を際立たせる要素、特徴」という意味になりました。
- 特にフォーマルな文脈や、学術・研究の場面で「ある人・物が持つ注目すべき特徴」を表す時に使われます。カジュアルな日常会話でも、相手の性格や特性を指摘する際に用いられることがありますが、少し硬い印象を与えることもあります。
- 口語でも使えますが、やや専門的・文語的ニュアンスを含むため、新聞やレポートなどの文章でよく見られます。
- 可算名詞: a trait / traits
例: “He has a distinct trait that sets him apart from others.” - 主に修飾語(new, interesting, negative, etc.)を伴い、形容詞+traitや名詞+traitの形で使われます。
- S + have/possess + (adjective) trait.
例: “She possesses a remarkable trait of compassion.” - It is a (adjective) trait (of + 名詞).
例: “It is a defining trait of great leaders.” “I believe kindness is her most admirable trait.”
(彼女の一番素晴らしい特徴は優しさだと思う。)“His honesty is not just a trait, it’s part of who he is.”
(彼の正直さは単なる特徴ではなく、彼自身を表すものだ。)“One trait I appreciate in a friend is a good sense of humor.”
(友達に求める特徴の一つは、優れたユーモアのセンスです。)“A key leadership trait is the ability to motivate a team effectively.”
(リーダーシップの重要な特徴の一つは、チームを効果的に鼓舞する能力です。)“Reliability is a crucial trait for any successful partnership.”
(信頼性はあらゆる成功するパートナーシップにとって重要な特徴です。)“This trait sets our product apart from the competition.”
(この特徴こそが、当社の商品を競合他社から際立たせます。)“Psychologists often study personality traits to understand human behavior.”
(心理学者は人間の行動を理解するために、しばしば人格特性を研究します。)“The inherited trait can be traced through several generations.”
(この遺伝的特性は何世代にもわたって辿ることができます。)“Researchers propose that this trait evolved as a survival mechanism.”
(研究者らは、この特性が生存のためのメカニズムとして進化したと提唱しています。)- characteristic(特徴): より概念的、広範な意味で用いられる
- feature(特徴): 外見的または顕著な点にフォーカスすることが多い
- attribute(属性): そのものに備わる本質的・付帯的な属性
- quality(質・品質・特質): より評価的なニュアンスが含まれることもある
- aspect(側面): 「特性」というよりは「側面」として対象を捉える場面で使われる
- 厳密な反意語はありませんが、文脈によっては「defect」(欠陥) や「fault」(短所)が「望ましくない特徴」というニュアンスで対比される場合があります。
- IPA: /treɪt/
- アクセント: 単音節語なので全体的に強く発音します。
- アメリカ英語 / イギリス英語での違い: 両方とも /treɪt/ が主流ですが、まれに /treɪ/ と発音する地域・話者もいます。
- よくある間違い: “treat”(/triːt/「ごちそう・おやつ・扱う」)や “threat”(/θrɛt/「脅威」)と混同しないように注意が必要です。
- スペルミス: “trait” と “treat” は綴りも似ているので混同しがち。
- 同音異義語との混同: “traite”というスペルは英語にはほぼ登場しませんが、フランス語では形が若干異なる発音の類語があります。
- 試験対策: TOEICや英検などのリーディングセクションで、人物や製品の長所を述べる文章に頻出します。キーワードとして出やすい単語なので、意味を把握しておくと読解力が向上します。
- 「一本の線」= 「特徴を描き出す」
「trait」という語源が「線を描く」ことに由来するイメージから、「誰か・何かがどういう線を持っているか」という感覚で覚えると定着しやすいです。 - スペリングに注意: “trait”が「1本の線(i)が T で線を引いて終わった」とイメージしておくと、“treat”との取り違えを防ぎやすくなります。
- 学習テクニック: 誰かの性格を分析するとき、「This person’s traits are…」と声に出して言ってみると自然に覚えられます。
英語の意味:
- (形容詞) Lower in rank or position; subject to the authority of another.
- (名詞) A person who is under the authority or control of another within an organization.
- (動詞) To treat or regard as of lesser importance compared to something else.
- (形容詞) Lower in rank or position; subject to the authority of another.
日本語の意味:
- (形容詞) 「下位の」「従属する」「~の下にある」
- 例:「ある組織や人に階層的に従属している様子を表します。上司や上位者がいて、それに対して下位に位置づけられる、というニュアンスです。」
- (名詞) 「部下」「下位にいる人」
- 例:「会社で言えば上司に対して部下を指すときに使います。上位の人の指示に従う立場の個人を表します。」
- (動詞) 「~を従属させる」「~を下位におく」
- 例:「ある目的や対象のために、ほかのものを二次的なものとして扱うイメージです。」
- (形容詞) 「下位の」「従属する」「~の下にある」
- 形容詞: subordinate (比較級や最上級の形はあまり用いられません)
- 名詞: subordinate (複数形: subordinates)
- 動詞: subordinate – subordinated – subordinated – subordinating
- 名詞形: subordination (従属、服従)
- 形容詞形: subordinative (文法用語として「従属の」の意でも使われることがあります)
- B2(中上級): 実務的なコミュニケーションや、仕事での意思疎通に使える単語。ビジネスやアカデミックな文脈でよく出てきます。
- sub-: 「下に」「下位の」を表す接頭語
- ordinate: 「秩序づける」「序列をつける」という意味を持つラテン語由来の語根 (ordinare = 「整える、序列をつける」)
- subordination (名詞): 従属、服従
- subordinate clause (文法用語): 従属節
- suborn (動詞): (法律で)偽証をそそのかす(「sub-」+「orn」由来で語源は少し異なりますが、部分的に似た形式です)
- subordinate role(従属する役割)
- subordinate position(下位の立場)
- subordinate staff(部下、下位のスタッフ)
- be subordinate to someone(〜の下位に属している)
- subordinate clause(従属節)
- treat something as subordinate(何かを従属的に扱う)
- subordinate relationship(従属関係)
- subordinate interest to(〜に対して利益を二の次にする)
- subordinate authority(下位の権限)
- subordinate function(下位の機能、補助的役目)
- sub-(下に)
- ordinare(順序づける)
- 上下関係やヒエラルキーを意識させるため、ビジネス文書や公的な場面でよく使われます。
- 口語では比較的フォーマルに聞こえるため、日常会話よりもオフィスやアカデミックなテーマで耳にすることが多いです。
- 特に「部下」という名詞としての意味はビジネスシーン先行ですが、形容詞/動詞としては「従属させる」「下位にある」を示します。
形容詞的用法
He holds a subordinate position in the company.
- 「彼はその会社で下位のポジションに就いている。」
- 「彼はその会社で下位のポジションに就いている。」
名詞的用法 (可算名詞)
He is one of my subordinates.
- 「彼は私の部下の一人です。」
- 「彼は私の部下の一人です。」
- 可算名詞なので “subordinates” と複数形にすることができます。
動詞的用法 (他動詞)
They always try to subordinate personal interests to the common good.
- 「彼らは常に個人の利益を公共の利益に従属させようとする。」
- 「彼らは常に個人の利益を公共の利益に従属させようとする。」
- 後ろに「目的語」をとって、「~を従属させる」という意味になります。
- “be subordinate to” ・・・ (形容詞的表現) 「~の下位にある」「~に服従する」
- “subordinate something to something” ・・・ (動詞表現) 「~を…に従属させる/優先順位を下げる」
I feel like my opinions are always subordinate to my brother’s.
- 「私の意見はいつも兄(弟)の意見より下に見られている気がする。」
- 「私の意見はいつも兄(弟)の意見より下に見られている気がする。」
In a family, children are usually subordinate to their parents.
- 「家族内では、子どもは通常親に従属する立場にあるよね。」
- 「家族内では、子どもは通常親に従属する立場にあるよね。」
That’s just a subordinate issue; let’s focus on the main problem first.
- 「それは些末(さまつ)な問題だから、まずは主要な問題に集中しよう。」
My subordinates are highly motivated and cooperative.
- 「私の部下はモチベーションが高く、協力的です。」
- 「私の部下はモチベーションが高く、協力的です。」
You need to learn how to delegate tasks to your subordinates effectively.
- 「部下に仕事を効果的に任せる方法を学ぶ必要があります。」
- 「部下に仕事を効果的に任せる方法を学ぶ必要があります。」
We should not subordinate employee well-being to short-term profits.
- 「従業員の幸福を短期的な利益に従属させるべきではありません。」
Many studies examine how individuals subordinate personal desires to group norms.
- 「多くの研究では、人がどのように個人的欲求を集団規範に従属させるかを検証しています。」
- 「多くの研究では、人がどのように個人的欲求を集団規範に従属させるかを検証しています。」
In complex sentences, a subordinate clause provides additional information.
- 「複文では、従属節が付加的な情報を提供します。」
- 「複文では、従属節が付加的な情報を提供します。」
Historically, certain social classes were considered subordinate in feudal societies.
- 「歴史的には、封建社会において特定の社会階層が従属的と見なされていました。」
- inferior (下位の、劣っている)
- 「下位である」ニュアンスが強く、能力的・価値的に「劣る」印象も与えます。
- 「下位である」ニュアンスが強く、能力的・価値的に「劣る」印象も与えます。
- junior (年下の、下位の)
- 「年齢や職位で下」であることを示す場合に使われます。
- 「年齢や職位で下」であることを示す場合に使われます。
- underling (下っ端、子分)
- やや口語的・ネガティブな響きが強い言い方です。
- やや口語的・ネガティブな響きが強い言い方です。
- assistant (助手)
- 下位というより、「補助する役割」を意味する場合に使われます。
- 下位というより、「補助する役割」を意味する場合に使われます。
- superior (上位の、上司)
- もっとも直接的な反意語。
- もっとも直接的な反意語。
- boss (上司)
- 口語的な「上司」。subordinate の対比語としてビジネスの現場などでよく使われる。
- 口語的な「上司」。subordinate の対比語としてビジネスの現場などでよく使われる。
- equal (対等の)
- 「上下関係がない」ニュアンスになります。
発音記号(IPA)
- (形容詞・名詞) /səˈbɔːr.dɪ.nət/ (アメリカ英語) /səˈbɔː.dɪ.nət/ (イギリス英語)
- (動詞) /səˈbɔːr.dɪ.neɪt/ と /səˈbɔː.dɪ.neɪt/
- (形容詞・名詞) /səˈbɔːr.dɪ.nət/ (アメリカ英語) /səˈbɔː.dɪ.nət/ (イギリス英語)
アクセント(強勢)の位置
- 「bo」または「bor」の部分に強勢がきます (su-BOR-di-nate)。
- 「bo」または「bor」の部分に強勢がきます (su-BOR-di-nate)。
アメリカ英語とイギリス英語での違い
- 形容詞・名詞形は大きな違いはありませんが、母音の発音にわずかな違いがある場合があります。
- 動詞形は語尾が “-ate” (エイト) となる発音が特徴的です。
- 形容詞・名詞形は大きな違いはありませんが、母音の発音にわずかな違いがある場合があります。
よくある発音の間違い
- “sub” の部分を強く発音し過ぎたり、 “bor” をあいまいにすると聞き取りづらくなります。
- スペルミス: “subordinate” の真ん中の “d” が抜けたり、「subordinate」を「subordnate」としてしまうなどのミスがよくあります。
- 同音異義語との混同: 類似した単語で同音異義語はあまりありませんが、「subordination」と混乱して、スペルや文法形を間違えないよう注意が必要です。
- 試験対策: TOEICや英検のリーディング、ビジネス英語問題などで「役職・階層」について问われる文章中に出てくる可能性があります。文法問題では「subordinate clause (従属節)」に関する問題もよく見かけます。
- “sub” = 下、 “or” = 順番、 “din” = 音の節(イメージで覚えると面白い)、 “ate” = 「~にする」
→ 「下位に順番を置く」というイメージを頭に入れると覚えやすいです。 - イメージストーリー: 「チームの中で部下(subordinate)は、上司(superior)の下に位置し、指示を受ける。」と関連づけて覚えると、どの品詞でも「下に位置づける」ニュアンスがあると理解しやすいです。
- スペル: 「sub」「ordin」「ate」を意識して区切って覚えると書き間違いを防げます。
- 「定期購読する」, 「サービスやチャンネルなどに申し込む」
- 「(意見や考えなどに)賛同する」
- 雑誌やサービスを定期的に利用するためにお金を払う、または登録すること。
- ある考えや意見に同意すること。
- 原形: subscribe
- 三人称単数現在形: subscribes
- 過去形: subscribed
- 過去分詞: subscribed
- 現在分詞/動名詞: subscribing
- 名詞: subscriber (定期購読者、加入者)
- 形容詞形はありませんが、subscribeに関連する形容詞として “subscribed (to ~)” のような受動態表現が使われることがあります。
- 接頭語: sub- (「下に、下位の」)
- 語幹: scrib (「書く」)
- 接尾語: -e (動詞を作る語尾)
- subscribe to a magazine(雑誌を定期購読する)
- subscribe to a channel(チャンネルを登録する)
- subscribe to a newsletter(ニュースレターを購読する)
- subscribe to an idea(ある考えに賛同する)
- subscribe for updates(更新情報を購読する)
- subscribe monthly(月額で購読する)
- subscribe to a streaming service(ストリーミングサービスを契約する)
- subscribe via email(メールで購読する)
- subscribe to a podcast(ポッドキャストを購読する)
- subscribe to our service(弊社のサービスを登録する)
語源:
ラテン語の “subscribere” (sub-「下に」+ scribere「書く」) に由来します。もともとは「文書の下に署名する」ことを指していました。歴史的使用:
署名する・同意する → 定期的にサービスや情報を受け取るための申し込み → さらに現代ではSNSやYouTubeなどの「フォロー・購読する」という意味合いに広がっています。ニュアンス・注意点:
- 「subscribe to an idea」のように「意見や理念に賛同する」という文脈でも使われる点が特徴的です。
- 口語でも使われますし、ビジネス上のメールや広告文など、かしこまった文面でもよく見られるので、カジュアル・フォーマルどちらでも使えます。
- 「subscribe to an idea」のように「意見や理念に賛同する」という文脈でも使われる点が特徴的です。
文法上のポイント:
- 通常は “subscribe to + 名詞” の形をとります。
- 他動詞のように目的語を直接取るというより、“to” という前置詞とセットで目的に「~を購読する、~に同意する」という意味を表します。
- 「subscribe for + 名詞」という形も見られますが、広告やキャンペーンなど「何に対して申し込むのか」を明確にしたい場合に用いられることが多いです。
- 通常は “subscribe to + 名詞” の形をとります。
イディオムやよくある表現:
- “Subscribe to this channel!”(このチャンネルを登録してね!)
- “I subscribe to your point of view.”(あなたの意見に同意します)
- “Subscribe to this channel!”(このチャンネルを登録してね!)
“I just subscribed to a new cooking magazine.”
「新しい料理雑誌を定期購読したよ。」“Don’t forget to subscribe to the YouTube channel for more videos.”
「もっと動画を見たいなら、YouTubeチャンネルを登録するのを忘れないでね。」“I totally subscribe to the idea that we should exercise every day.”
「毎日運動すべきだっていう考えに完全に同意するよ。」“Our company has subscribed to a project management tool to improve workflow.”
「我が社はワークフローを改善するためにプロジェクト管理ツールを契約しました。」“You can subscribe to our premium plan for additional features.”
「追加機能をご利用いただくには、プレミアムプランをご契約いただけます。」“If you agree with our mission, we invite you to subscribe to our newsletter.”
「私たちのミッションに賛同してくださるのであれば、ニュースレターの購読をお勧めします。」“Many researchers subscribe to the theory that climate change is accelerating.”
「多くの研究者は、気候変動が加速しているという理論に賛同しています。」“Students can subscribe to academic journals at a discounted rate.”
「学生は学術雑誌を割引料金で定期購読できます。」“While some scholars subscribe to this hypothesis, others remain skeptical.”
「この仮説を支持する学者がいる一方で、懐疑的な研究者もいます。」- sign up (申し込む)
- 通常はサービスやイベントへの参加登録を指し、日常的で広い文脈で使われる。
- 通常はサービスやイベントへの参加登録を指し、日常的で広い文脈で使われる。
- register (登録する)
- 行政的・公式的な文脈でもよく使われる。
- 行政的・公式的な文脈でもよく使われる。
- pledge (誓約する/支援を約束する)
- 「誓約する」「寄付や支援を約束する」という意味が強い。
- 「誓約する」「寄付や支援を約束する」という意味が強い。
- support (支持する)
- 賛同や援助のニュアンスが強く、寄付や後援などにも使われる。
- 賛同や援助のニュアンスが強く、寄付や後援などにも使われる。
- endorse (公に承認する)
-ややフォーマルな響きがあり、著名人が商品の広告で賛成や承認を示すときなどに用いられる。 - unsubscribe (解除する)
- opt out (加入/参加を辞退する)
- disavow (否認する、支持を撤回する)
- 発音記号 (IPA): /səbˈskraɪb/
- 第二音節 “-scribe” にアクセントがあります。
- 第二音節 “-scribe” にアクセントがあります。
- アメリカ英語 / イギリス英語: 発音に大きな違いはほぼありませんが、イギリス英語で [səbˈskraɪb]、アメリカ英語で [səbˈskraɪb] のように発音され、口の開き方や「r」の発音が多少異なることがあります。
- よくある発音の間違い:
- 第一音節 “sub” の母音「ʌ」を「uː」などの長音で読んでしまうことがあるので注意します。
- “scribe” の “s” と “c” の位置を曖昧に発音しないように気をつけましょう。
- 第一音節 “sub” の母音「ʌ」を「uː」などの長音で読んでしまうことがあるので注意します。
- スペルミス: “subsrcibe” や “subscrive” など、sとcの位置を間違える例が多いです。
- 同音異義語との混同: “prescribe”(処方する) とか “describe”(説明する) など、-scribe 系の動詞とごっちゃにならないよう注意。
- 試験での出題傾向:
- TOEIC や 英検 などのリスニング・リーディングで、契約や購読に関する設問で出てくる可能性がある。
- “subscribe to the theory/idea” の用法も、論説文などで問われる場合があります。
- TOEIC や 英検 などのリスニング・リーディングで、契約や購読に関する設問で出てくる可能性がある。
- 語源をイメージ: “sub- (下に)” + “scribe (書く)” → 「下にサインをする」 → 「定期購読・賛同する」だから “subscribe”
- 勉強テクニック:
- ほかの “-scribe” 系単語 (describe, prescribe, inscribe, etc.) とまとめて、小さな語根 “scrib(e) = 書く” でグループ学習すると覚えやすい。
- YouTubeなどで「Subscribe!」とよく目にするはずなので、サービス登録やチャネル登録をイメージすると覚えやすいです。
- ほかの “-scribe” 系単語 (describe, prescribe, inscribe, etc.) とまとめて、小さな語根 “scrib(e) = 書く” でグループ学習すると覚えやすい。
- スペルの注意: 「sub」と「scribe」の2つで区切って覚えるとミスが減る。
- 原形: publish
- 三人称単数現在形: publishes
- 現在分詞・動名詞: publishing
- 過去形・過去分詞: published
- 名詞: publisher(出版者)、publication(出版、刊行物)
- 形容詞形(派生的に “published” などが形容詞として使われる場合あり)
- 接頭語: 特になし
- 語幹: “publish” は “public”(公共の)と関連するラテン語に由来
- 接尾語: 特になし
- 書籍や雑誌などを正式に刊行する
- 研究結果や論文、情報などを一般に広く公開する
- publish a book(本を出版する)
- publish an article(記事を掲載する / 論文を発表する)
- publish findings(研究成果を公表する)
- publish results(結果を公表する)
- publish a paper(論文を発表する)
- publish online(オンラインで公開する)
- publish new editions(新しい版を出版する)
- publish data(データを公表する)
- publish a statement(声明を発表する)
- publish a newsletter(会報を発行する)
- 学術論文や研究成果を「公表する」場合に使われると同時に、商業出版物を「出版する」場合にも幅広く使われます。
- 「情報を正式に外部へ発信する」という響きがあるため、ビジネス文書でも多用されます。
- 口語でも使われますが、どちらかというとフォーマル・ビジネスよりの単語です。
他動詞としての使い方
- ほとんどの場合は目的語を伴い、「(人が) 何かを出版・発表する」という形で使われます。
- 例: “The company published its annual report.” (会社は年次報告書を発表した)
- ほとんどの場合は目的語を伴い、「(人が) 何かを出版・発表する」という形で使われます。
自動詞としての使い方
- 稀に「刊行される」「公にされる」というニュアンスで用いられることがあるが、受動態 “be published” が一般的です。
- 例: “The results publish next month.” (※形式上少々硬い/古風)
- ほぼ “The results will be published next month.” が普通。
- 稀に「刊行される」「公にされる」というニュアンスで用いられることがあるが、受動態 “be published” が一般的です。
一般的な構文・イディオム
- “publish or perish”
- 主にアカデミックな世界で、研究者が論文を発表しないと評価されない(または地位を保てない)という文脈で使われるフレーズ。フォーマルで専門色が強い。
- “publish or perish”
“I heard you’re going to publish your recipes online. That’s so exciting!”
- 「あなたがレシピをオンラインで公開するって聞いたよ。とても楽しみだね!」
“My friend wants to publish her poetry on her blog next month.”
- 「友達は自分の詩を来月ブログで発表したいと思っているんだ。」
“Do you ever think about publishing your travel photos in a magazine?”
- 「雑誌に旅行写真を載せてみたいと思ったことはある?」
“Our company plans to publish the new product catalog by the end of the quarter.”
- 「当社は四半期末までに新しい製品カタログを発行する予定です。」
“We need to publish a press release about the merger as soon as possible.”
- 「合併に関するプレスリリースを、できるだけ早く発表する必要があります。」
“They decided not to publish the financial data until the audit is complete.”
- 「監査が終了するまで、彼らは財務データを公表しないことに決めました。」
“He’s going to publish his latest research in a reputable journal.”
- 「彼は最新の研究を権威ある学術誌に発表する予定です。」
“Before you can graduate, you often have to publish at least one paper.”
- 「卒業する前に、少なくとも1本の論文を発表しなければならないことが多いです。」
“The lab will publish its groundbreaking findings next month.”
- 「その研究室は画期的な成果を来月公表する予定です。」
release(公表する/リリースする)
- 「新情報や製品のリリース」を強調。
- 例: “The company released a new software update.” (「会社は新しいソフトウェアアップデートをリリースした」)
- 「新情報や製品のリリース」を強調。
issue(刊行する/発行する)
- 政府や機関が公式に「発行する」というニュアンス。
- 例: “The government issued an official statement.” (「政府は公式声明を発表した」)
- 政府や機関が公式に「発行する」というニュアンス。
print(印刷して出版する)
- 紙媒体への印刷にフォーカス。
- 例: “They printed 1,000 copies of the magazine.” (「彼らは雑誌を1,000部印刷した」)
- 紙媒体への印刷にフォーカス。
announce(発表する)
- お知らせ的に口頭や文章で「公に伝える」。
- 例: “He announced his intention to run for office.” (「彼は出馬する意向を発表した」)
- お知らせ的に口頭や文章で「公に伝える」。
distribute(分配する/配布する)
- 「配る」というニュアンスが強い。
- 例: “They distributed copies of the new policy.” (「新しい方針のコピーを配布した」)
- 「配る」というニュアンスが強い。
conceal(隠す)
- 公開しない、隠蔽する。
- 例: “They decided to conceal the true identity of the witness.” (「彼らは証人の本当の身元を隠すことにした」)
- 公開しない、隠蔽する。
withhold(差し止める/保留する)
- 公表を差し控える。
- 例: “The company withheld the negative test results.” (「会社はその不利なテスト結果を公表しなかった」)
- 公表を差し控える。
- 発音記号 (IPA): /ˈpʌblɪʃ/
- アクセント位置: 最初の “pub” に強勢が置かれます(PUB-lish)。
- アメリカ英語とイギリス英語の違い: 基本的に同じ発音ですが、イギリス英語のほうが “ʌ” がやや短めで、アメリカ英語ではもう少し太めに発音される傾向があります。
- よくある発音の間違い: 「パブリッシュ」と「パブリック」の混同。 “publish” は [lɪʃ] の末尾が “リッシュ” となるよう意識しましょう。
- スペリングミス: 「publisch」「publis」などとするミスが多い。
- 同音異義語との混同: 同音異義語は特にないが、似た単語 “public” と混同しないよう注意。
- 熟語との誤用: “publish or perish” をただ「発刊しないと滅びる」と直訳してしまうと誤解のもとになる。学術論文などの世界独特の表現。
- 資格試験での出題: TOEICや英検などでは、ビジネス文書やニュース記事などの文脈で「発行する」「公表する」を問う際によく使われる。
- “publish” は “public” に関連して「公にする」が語源。
- 「パブリック(公共)」に向けて情報を出す → “publish” とイメージすると覚えやすい。
- 音が似ている「パブリック(public)」とのつながりを意識し、発音・スペリングの違いを明確に押さえると混乱しにくい。
- 本や記事を「世に出す」=「publish」と連想して覚えると良いです。
- To gather or collect something over time; to increase in quantity or number gradually.
- 積み重ねる、蓄積する、少しずつ集める。
「長い時間をかけて徐々に増やしていく、というニュアンスの動詞です。物理的に何かを貯める場合もありますし、経験や知識など目に見えないものを貯めるイメージでも使われます。」 - 原形: accumulate
- 三人称単数現在形: accumulates
- 現在分詞/動名詞: accumulating
- 過去形/過去分詞: accumulated
- 名詞: accumulation (蓄積)
- 例: “There was an accumulation of dust on the shelf.”
- 例: “There was an accumulation of dust on the shelf.”
- B2(中上級): 比較的抽象的な状況でも使われる語で、ビジネスや学術でもよく登場します。
- ac- (ad-): 「~へ」とか「~に向かって」というラテン語由来の接頭語の変化形
- cumul: 「山」「積み重ね」の意を持つ語根(ラテン語の
cumulus
= heap, pile) - -ate: 動詞化する接尾語
- accumulation (名詞): 蓄積
- accumulative (形容詞): accumulative data(蓄積されたデータ)のように「蓄積の」「蓄積的な」を表す
- accumulator (名詞): 蓄積するもの、蓄電池を指すこともある
- accumulate wealth (富を蓄積する)
- accumulate evidence (証拠を集める)
- accumulate knowledge (知識を蓄える)
- accumulate points (ポイントを貯める)
- accumulate data (データを蓄積する)
- gradually accumulate (徐々に蓄積する)
- an accumulated debt (積み重なった借金)
- accumulate assets (資産を蓄える)
- accumulate experience (経験を積む)
- accumulate overtime hours (残業時間を重ねる)
- ラテン語の「ad-」(~へ、~に向かって)+「cumulare」(山状に積み重ねる)から派生。
- 元々は「積み重ねていく」という物理的なイメージが強かったが、現代では抽象的なもの(経験・知識・負債など)を含む幅広い対象に使用。
- 積み上げるという行為が焦点となるので、「こつこつ集める、時間をかけて増やす」という印象を与えます。
- 口語でも文章でも使われますが、ややフォーマル寄りの文脈でよく見られます。
他動詞・自動詞の両方で使えます。
- 他動詞: “He accumulated a large collection of comics.”(彼はたくさんの漫画を集めた。)
- 自動詞: “Dust accumulated on the bookshelf.”(本棚の上にほこりが積もった。)
- 他動詞: “He accumulated a large collection of comics.”(彼はたくさんの漫画を集めた。)
フォーマル度: ややフォーマルに使われる場合が多いが、日常会話でも問題なく使える。
ビジネス文書やアカデミックな文献で頻出。
- “accumulate over time” : 時間と共に蓄積される
- “slowly accumulate” : 徐々に増す/蓄積する
- “I have accumulated so many photos on my phone; I need to delete some.”
- 「スマホに写真がたまりすぎたので、削除しないといけないな。」
- “Dust quickly accumulates if you don’t clean the room regularly.”
- 「部屋をこまめに掃除しないと、ほこりがすぐにたまるよ。」
- “She’s accumulated a lot of cooking tips by watching online videos.”
- 「彼女はオンライン動画を見て、料理のコツをたくさん身につけたんだ。」
- “We plan to accumulate more market data before launching our new product.”
- 「新商品を発売する前に、さらに市場データを集める予定です。」
- “The company accumulated significant debt due to poor investment decisions.”
- 「その会社は投資の失敗により、かなりの負債を抱え込んでしまった。」
- “Our goal is to accumulate enough funds to expand overseas.”
- 「海外進出をするのに十分な資金を蓄えるのが、私たちの目標です。」
- “Over centuries, scientists have accumulated evidence supporting the theory of evolution.”
- 「何世紀にもわたり、科学者たちは進化論を裏付ける証拠を蓄積してきた。」
- “Data on climate change continues to accumulate, pointing to significant global warming.”
- 「気候変動に関するデータが蓄積され続け、深刻な地球温暖化を示している。」
- “Through careful research, scholars endeavor to accumulate scholarly consensus on this issue.”
- 「綿密な研究を通じて、学者たちはこの問題に関する学術的な合意を形成しようとしている。」
- gather(集める)
- 「手で一つ一つ集めるイメージ。accumulateよりもカジュアル。」
- 「手で一つ一つ集めるイメージ。accumulateよりもカジュアル。」
- amass(蓄える)
- 「大きな量を手に入れる、特に富や財産を集める文脈でよく用いられる。accumulateよりもややフォーマル。」
- 「大きな量を手に入れる、特に富や財産を集める文脈でよく用いられる。accumulateよりもややフォーマル。」
- collect(集める)
- 「趣味や仕事で意識的に収集する感じ。accumulateよりも意図的である場合が多い。」
- 「趣味や仕事で意識的に収集する感じ。accumulateよりも意図的である場合が多い。」
- pile up(積み上げる)
- 「カジュアルな表現。物理的に物が積み重なっていくニュアンスが強い。」
- disperse(散らす、散乱させる)
- dissipate(散らす、消散させる)
- IPA: /əˈkjuː.mjə.leɪt/
- 強勢はcu(“kyu”)の部分にあります。
- アメリカ英語・イギリス英語ともに大きな差異はありませんが、イギリス英語では /ˈkjuː.mjə-/ とやや明瞭に発音されることがあります。
- しばしば “accummulate” のように “m” を重ねすぎるスペルミスや、アクセント位置を誤って“a-CCU-mu-late”と言う間違いが起こりがちです。
- スペルミス: “accumulate” は “m” が1つ、“c” が2つであることを注意。
- 発音: “アキュミュレイト”のように強勢をしっかり第二音節に置く。
- 混同しやすい単語: “acculturate” (文化に適応する) や “accumulate” は形が似ているので注意。
- 試験対策: TOEICや英検でビジネス文脈や環境・経済などの論説文中に出やすい単語。多義的な文章で「AがBを蓄積する」という流れがよく登場する。
- ラテン語の “ad-” + “cumulus” で “山の方へ積み重ねていく” というイメージを思い浮かべると覚えやすいです。
- “A cup you late(ア カップ ユ レイト)” のように区切って暗記する人もいますが、語源を意識したほうがしっかり定着します。
- 「少しずつ雪だるまが大きくなるイメージ」で覚えると、自然に“accumulate”のニュアンスが伝わります。
- 現在形: depart / departs (三人称単数)
- 過去形: departed
- 過去分詞形: departed
- 現在分詞形: departing
- このレベルは、ある程度複雑な文章や抽象的な話題にも対応できる英語力が必要です。
- 名詞: departure(出発、発車、離脱)
- 例: “The departure time is 10 a.m.”(出発時刻は午前10時です)
- 例: “The departure time is 10 a.m.”(出発時刻は午前10時です)
- 過去分詞/形容詞的用法: departed(死去した、故~)
- 例: “the departed souls”(亡くなった方々)
- 「下に」「離れて」「否定」を示すことが多く、この場合は「離れる」というニュアンスを強調。
- 「分ける」「分割する」の意味をもつラテン語に由来。英語の“part”や“partial”、“partition”などにも関連。
- depart from somewhere
- 和訳: (どこかを)出発する
- 和訳: (どこかを)出発する
- depart for somewhere
- 和訳: (どこかへ)向けて出発する
- 和訳: (どこかへ)向けて出発する
- depart at (time)
- 和訳: (何時)に出発する
- 和訳: (何時)に出発する
- depart this life
- 和訳: 世を去る(やや文語的・婉曲表現)
- 和訳: 世を去る(やや文語的・婉曲表現)
- scheduled to depart
- 和訳: 出発予定である
- 和訳: 出発予定である
- depart on business
- 和訳: 出張に出る
- 和訳: 出張に出る
- depart early
- 和訳: 早めに出発する
- 和訳: 早めに出発する
- depart late
- 和訳: 遅れて出発する
- 和訳: 遅れて出発する
- depart from the norm
- 和訳: 通常のやり方から離れる(慣用的に幅広く使われる)
- 和訳: 通常のやり方から離れる(慣用的に幅広く使われる)
- depart terminal gate
- 和訳: (空港などの)ゲートから出発する
- 和訳: (空港などの)ゲートから出発する
- ラテン語の “dēpartīre” (de-「離れる」+ partīre「分ける」) に由来し、「分かれて離れる」というニュアンスが根底にあります。英語でも中世期には「分割する」という意味合いもありましたが、現在では主に「出発する」という意味で使用されます。
- 「depart」は“leave”よりも少しフォーマルで、鉄道や飛行機のアナウンス、政府や公的機関からの情報などに使われることが多いです。
- 日常会話でも使えますが、「leave」の方が自然なことも多いです。文書やニュース、案内放送での使用が比較的高い頻度を占めます。
- 自動詞 (intransitive verb): 対象に関わらず「出発する」「離れる」の意味で使われる。
- 例: “The train departs at 9 a.m.” (この場合、目的語を直接取らず、時刻や場所を補足的に付ける)
- 例: “The train departs at 9 a.m.” (この場合、目的語を直接取らず、時刻や場所を補足的に付ける)
- 前置詞 “from”を使って「〜から出発する」を表現できる。また “for”を使って「〜に向かって出発する」を示す。
- フォーマル/半フォーマル: “depart” は公共のアナウンスや公的文書でよく使われる。
- カジュアル/口語: 日常会話では “leave” や “take off” (飛行機の場合) の方が自然なことも多い。
- “depart from the usual path/way” 「いつものやり方から逸脱する」
- “depart this life” 「(死んで)この世を去る」(文語的)
- “I’m going to depart from home at 8 a.m. to avoid rush hour.”
- (ラッシュアワーを避けるために、朝8時に家を出るつもりだよ。)
- (ラッシュアワーを避けるために、朝8時に家を出るつもりだよ。)
- “We should depart soon if we want to catch the first train.”
- (始発に乗りたければ、そろそろ出発したほうがいいよ。)
- (始発に乗りたければ、そろそろ出発したほうがいいよ。)
- “Let’s depart after breakfast, so we have enough energy for the trip.”
- (朝食後に出発しよう。旅に備えて十分なエネルギーをつけておきたいから。)
- “The sales team will depart for the convention on Thursday morning.”
- (営業チームは木曜の朝にその大会へ向けて出発します。)
- (営業チームは木曜の朝にその大会へ向けて出発します。)
- “Please check the flight details carefully before you depart.”
- (出発前にフライトの詳細をよく確認してください。)
- (出発前にフライトの詳細をよく確認してください。)
- “We plan to depart the office around 2 p.m. for our client visit.”
- (顧客訪問のため、午後2時ごろオフィスを出発する予定です。)
- “The research team will depart from the base camp to collect samples in the early morning.”
- (調査チームは早朝にベースキャンプを出発してサンプルを収集する予定です。)
- (調査チームは早朝にベースキャンプを出発してサンプルを収集する予定です。)
- “The study departs from the traditional methodology, employing an innovative approach.”
- (その研究は従来の方法論から離れ、革新的手法を採用している。)
- (その研究は従来の方法論から離れ、革新的手法を採用している。)
- “All participants are required to submit their paperwork before they depart the symposium.”
- (シンポジウムを離れる前に、全参加者は書類を提出する必要があります。)
- leave(去る)
- もっとカジュアルで日常的。「depart」とほとんど同じ意味で使われるが、フォーマルさが異なる。
- もっとカジュアルで日常的。「depart」とほとんど同じ意味で使われるが、フォーマルさが異なる。
- exit(退出する)
- 場所から出るイメージが強く、より物理的なニュアンス。
- 場所から出るイメージが強く、より物理的なニュアンス。
- go away(どこかへ行く)
- 大まかに「立ち去る」「離れる」という意味。
- 大まかに「立ち去る」「離れる」という意味。
- set off(出発する)
- 旅の始まりを強調し、カジュアルにもよく使われる。
- arrive(到着する)
- 「depart」のまさに逆の動き。
- 「depart」のまさに逆の動き。
- come(来る)
- 自分の方へ「近づいてくる」動き。
- 自分の方へ「近づいてくる」動き。
- アメリカ英語: /dɪˈpɑːrt/
- イギリス英語: /dɪˈpɑːt/
- “departed” の /dɪˈpɑːrtɪd/ (ディパーティッド) の最後の t と d の音がつながり発音しづらいことがある。
- スペルミス: “depert” や “depard” などと誤記しないよう注意。
- 同音異義語との混同: “the departed” (死者、故人) という表現は文学的・文語表現で「亡くなった人々」を指す場合があるので意味を混同しないようにしましょう。
- TOEICや英検など試験での出題: 飛行機や旅行計画に関するパートで登場することが多い。「depart from ○○」「depart for ××」など前置詞の使い方に注意。
- 語源で覚える: “de” + “part” → “離れる + 分かれる” で「出発する」とイメージしやすい。
- イメージ連想: 出発ゲートや鉄道の時刻表など、公的なシーンで「depart」を目にする機会は多い。実際の旅行や時刻表をイメージしながら覚えるとよい。
- 勉強テクニック: “depart from A” と “depart for B” の形で前置詞とセットで何度も口に出して練習する -> 自然に言えるようになる。
- 英語: hydrogen – the chemical element with the symbol H; a colorless, odorless gas which is the lightest and most abundant element in the universe.
- 日本語: 水素 – 化学元素の一つで、元素記号は H。無色無臭の気体で、宇宙で最も軽く、最も豊富に存在する元素です。
- 不可算名詞なので、通常は単数形 “hydrogen” のままで扱います。
- 冠詞 (a, an, the) をつける場合は「the hydrogen molecule」のように特定の概念を示すときに使います。
- 動詞形の “to hydrogenate” (水添する) は別の意味になります (油脂に水素を添加するなど)。
- 名詞派生語として “hydrogenation” (水添反応) などがあります。
- B2 (中上級): 一般的な単語ではないものの、科学系のトピックで学習する語彙としては中上級レベルです。
- hydro-: ギリシャ語で「水」を意味する “hydōr (ὕδωρ)” に由来
- -gen: 「生成する」や「生じるもの」を意味するギリシャ語 “-genēs (γενής)” に由来
- hydrogenate (動詞): 水素添加する
- hydrogenation (名詞): 水素添加、水添反応
- hydronic (形容詞): 水を媒体とする暖房・冷房システムなどに関連した (hydro- + -ic, 水に関する)
- hydrogen bond → 水素結合
- hydrogen molecule → 水素分子
- hydrogen atom → 水素原子
- hydrogen fuel → 水素燃料
- hydrogen tank → 水素タンク
- liquid hydrogen → 液体水素
- hydrogen economy → 水素社会 / 水素エネルギー経済
- hydrogen storage → 水素貯蔵
- hydrogen production → 水素製造
- hydrogen vehicle → 水素自動車
- ギリシャ語の「水 (hydōr)」+「生じる (genēs)」が由来です。18世紀後半に命名され、水を生み出すガスという意味で定着しました。
- 科学分野を中心に登場する専門用語ですが、近年のクリーンエネルギー文脈でもよく使われます。
- フォーマルな文書だけでなく、ニュースや記事などでも見られるため、カジュアルかつ専門的な響きを持ちます。
- 「hydrogen」は不可算名詞です。通常は複数形になりませんし、数えられる対象として扱いません。
- 一般的には「some hydrogen」「a container of hydrogen」のように数量表現を間に挟んで用いることが多いです。
- “Hydrogen is the simplest element.”
- “We need to store hydrogen carefully.”
- 直接のイディオムは少ない一方、科学・技術文書では「hydrogen economy (水素エネルギー経済)」「hydrogen bond (水素結合)」など、複合的な名詞句で使われます。
- “I heard they’re developing cars that run on hydrogen.”
(水素で走る車を開発しているらしいよ。) - “Hydrogen is lighter than air, so it can make balloons float.”
(水素は空気よりも軽いから、風船を浮かせることができるんだよ。) - “They say hydrogen might be the fuel of the future.”
(水素は将来の燃料になるかもしれないって言われているよ。) - “Our company is investing in hydrogen fuel technology.”
(当社は水素燃料技術に投資しています。) - “We’re planning to expand into hydrogen production facilities.”
(私たちは水素製造施設への拡大を計画しています。) - “The conference will focus on hydrogen solutions for clean energy.”
(その会議ではクリーンエネルギーのための水素ソリューションに焦点が当てられます。) - “Hydrogen bonding plays a crucial role in the structure of DNA.”
(DNAの構造において、水素結合は極めて重要な役割を果たす。) - “The hydrogen spectrum provides valuable insights into quantum mechanics.”
(水素スペクトルは量子力学について貴重な見識を与えてくれる。) - “Researchers are investigating novel catalysts for hydrogen production.”
(研究者たちは新しい水素製造用触媒を研究している。) - “H” (Element Symbol): 元素記号で、科学論文や化学式で使われる。
- “fuel” (燃料): 直接の同義語ではありませんが、エネルギー源としての文脈で水素が燃料と並列して扱われることで関連性があると言えます。
- 本質的な反意語は無いですが、例えば“inert gases”(不活性ガス)と対比させることはあります(反応性が強い水素と、反応性が低い不活性ガスという違いで)。
- IPA: /ˈhaɪ.drə.dʒən/
- アメリカ英語・イギリス英語ともに大きく変わりません。
- アメリカ英語: /ˈhaɪ.drə.dʒən/
- イギリス英語: /ˈhaɪ.drə.dʒən/
- アメリカ英語: /ˈhaɪ.drə.dʒən/
- アクセントは最初の “hy-” の部分にあり、「ハイ」のように強く発音し、後ろに行くほど弱くなります。
- よくある間違いは、/dʒ/ の音を /g/ や /ʃ/ (シ音) と混同してしまうことです。
- スペル: “hydrogen” は “hydro-” と “-gen” の2つから成り立っていることを意識すると覚えやすいです。つづり間違いで “hydorgen” や “hydogen” になりがちです。
- 同音異義語との混同はほぼありませんが、「hydro-」が付く他の単語(hydrology, hydroponicsなど)と混同しないよう注意しましょう。
- 試験対策: TOEIC や英検などで直接出題される頻度は高くありません。しかし、科学技術や環境問題のトピックで文章を読解する際に出てくることがあります。文脈から「燃料」や「エネルギー源」を連想できるようにしておくとよいでしょう。
- 水 (hydro) + 生み出す (gen) → “水を生み出す” イメージを持ち続けると覚えやすいです。
- スペリングは「hydro」+「gen」をくっつけたものと考えるとミスが減ります。
- 「H2O(=水)の一部になる元素」と関連付けて覚えることで、忘れにくくなります。
- エネルギー文脈で学習するときは、次世代エネルギーとしての水素(hydrogen fuel cell など)をセットで覚えると理解が深まります。
- B1(中級)学習者でも触れる単語ですが、科学・技術分野で使われる専門的な文脈があるため、B2のレベル感としています。
- A device or instrument designed to investigate, explore, or examine something in detail (特に科学的・技術的な調査機器を指す)。
- An investigation or inquiry (特に事件や事実究明のための公式な調査も指す)。
- 「調査機器」「探査機」「探査装置」など、何かを詳しく調べるための道具を指します。
- 「調査」「探査」「捜査」という意味でも使われ、特に事件の捜査や深い調査に対して使われます。
「probe」は、科学実験や宇宙探査機などを指すときにも使われる、丁寧・専門的な言葉です。捜査や摘発の文脈では少しフォーマルな響きになります。 - 名詞形 (単数): a probe
- 名詞形 (複数): probes
- 動詞形: to probe (詳しく調査する、探る)
- 動詞: “to probe”
例: The detective probed into the suspect’s background. - 形容詞形: 派生形容詞はあまり一般的ではありませんが、“probing”(鋭く追及する、探求的な)として形容詞的に使われます。
- 語幹: “prob-” (「試す」「調べる」というニュアンス)
- 接頭語・接尾語: 接頭語・接尾語は特にない単語ですが、語幹をもとにした派生語として “probable” “probation” など、語源が「試す」に関連する単語があります。ただし、直接 “probe” と同じ意味ではありません。
- to probe (動詞): 探る、調べる、突き止める
- probing (形容詞): 詮索するような、追及するような
- “space probe” – 宇宙探査機
- “lunar probe” – 月探査機
- “probe into” – (事件など)を捜査する、調べる
- “NASA probe” – NASAの探査機
- “criminal probe” – 犯罪捜査
- “government probe” – 政府による捜査/調査
- “deep probe” – 深い探究、徹底調査
- “probe data” – 探査データ、調査データ
- “probe the surface” – 表面を探査する
- “ongoing probe” – 継続中の捜査/調査
- 科学的・技術的な文脈(宇宙探査機など)では中立的または専門的ニュアンスを持ちます。
- 事件やスキャンダルの捜査では、フォーマルでやや堅い印象があります。
- カジュアルな日常会話ではあまり頻繁に使われませんが、「詳しく調べる」というニュアンスを強調したい場合に使われます。
- 名詞としては可算名詞として用いられます (a probe, two probes)。
- 動詞として使われるときは「他動詞」扱いが多く、“probe something” (何かを徹底的に調査する) という形をとります。
- “probe into something” のように前置詞 “into” を伴って「~を詳しく調べる」という表現にもなります。
- “to launch a probe (into ~)” → 「(~への)調査を開始する」
- “to conduct a probe” → 「調査を行う」
- “a full-scale probe” → 「本格的な調査」
- “Did you hear they sent a probe to Mars last week?”
- 先週、火星に探査機を打ち上げたって聞いた?
- 先週、火星に探査機を打ち上げたって聞いた?
- “He started asking too many personal questions, like he was trying to probe into my private life.”
- 彼はプライベートを探るように、個人的なことを根掘り葉掘り聞いてきたんだ。
- 彼はプライベートを探るように、個人的なことを根掘り葉掘り聞いてきたんだ。
- “The doctor used a thin probe to check my ear canal.”
- 医者は細い探査器具を使って耳の奥を診察しました。
- 医者は細い探査器具を使って耳の奥を診察しました。
- “Our company is conducting a probe into the security breach to find out how it happened.”
- わが社はセキュリティ侵害が何故起こったのか突き止めるため、調査を行っています。
- わが社はセキュリティ侵害が何故起こったのか突き止めるため、調査を行っています。
- “The board launched a probe to ensure compliance with the new regulations.”
- 取締役会は新規則に対するコンプライアンスを確認するため、調査を開始しました。
- 取締役会は新規則に対するコンプライアンスを確認するため、調査を開始しました。
- “We hired an independent firm to probe the financial records for any discrepancies.”
- 不一致がないか財務記録を調べるため、外部の専門会社に調査を依頼しました。
- 不一致がないか財務記録を調べるため、外部の専門会社に調査を依頼しました。
- “The space probe successfully transmitted high-resolution images back to Earth.”
- 宇宙探査機は高解像度の画像を地球に無事送信しました。
- 宇宙探査機は高解像度の画像を地球に無事送信しました。
- “To study the ocean depths, researchers deployed a deep-sea probe that can withstand high pressure.”
- 海洋の深部を研究するため、研究者たちは高圧に耐えられる深海探査機器を使用しました。
- 海洋の深部を研究するため、研究者たちは高圧に耐えられる深海探査機器を使用しました。
- “An international team is conducting a probe into the origins of the ancient ruin.”
- 国際研究チームはその古代遺跡の起源を解明するため、徹底的な調査を行っています。
- 国際研究チームはその古代遺跡の起源を解明するため、徹底的な調査を行っています。
- “investigation” (調査)
- 一般的な「調査」を指し、「詳細に調べる」という広い意味。よりフォーマルかつ幅広く使われる。
- 一般的な「調査」を指し、「詳細に調べる」という広い意味。よりフォーマルかつ幅広く使われる。
- “inquiry” (問い合わせ、調査)
- 公的または公式な調査に用いることが多い。法的手続きなどの文脈でよく使われる。
- 公的または公式な調査に用いることが多い。法的手続きなどの文脈でよく使われる。
- “examination” (検査、試験)
- より具体的な検査・試験を指す。医療や学術分野でも用いられる。
- より具体的な検査・試験を指す。医療や学術分野でも用いられる。
- “ignore” (無視する)
- 「調べない」「探らない」という真逆の行為ですが、名詞としての反意語ははっきり存在しません。文脈によっては “neglect (無視、怠る)” と対比されることがあります。
- 発音記号 (IPA): /proʊb/ (米), /prəʊb/ (英)
- アクセント: 単音節語なので特別な強勢の移動はありません。語全体を一拍で “probe” と発音します。ただし、アメリカ英語では “oʊ” の二重母音が少し長めに発音されるイメージです。
- よくある間違い: 最後の “b” を発音し忘れる人がまれにいますが、しっかり「プローブ」と発音します。
- スペルミス: “probe” と “prob” や “prope” と誤記することがあるので注意しましょう。
- 同音異義語との混同: 一般的には “probe” に同音異義語は少ないですが、語尾が似ている “robe” (ローブ) などとは意味がまったく違うので注意。
- 試験での出題傾向: TOEICや英検などでは、ビジネスや科学分野の文章中に登場することがあります。なじみがないと誤読しやすいので注意が必要です。
- 語源イメージ: 「試す・証明する」というラテン語 “probare” から派生しているので、「何かを試験的に探すツールや調査」のイメージを持つと覚えやすいです。
- 勉強テクニック: 「問題・謎などをつついてみる」というイメージで、針の先や道具をイメージすると暗記に役立ちます。
- “space probe” (宇宙探査機) をキーワードとして覚えると、科学・技術分野でよく使われるイメージが強まり、定着しやすくなります。
- 単数形: obituary
- 複数形: obituaries
- B2(中上級)
新聞を読んだり、少し専門的な文章に触れるレベルで必要になることがある単語です。 - 接頭語/接尾語/語幹
- obit-(= “死” あるいは “亡くなったこと” を表す語根)
- -uary(= 形容詞や名詞を作る接尾語。英語ではしばしば「~に関するもの/場所/記事」の意味を含む)
- obit-(= “死” あるいは “亡くなったこと” を表す語根)
- obit: 「死亡、逝去」という意味で、新聞などでは「obit」という略語で死亡記事のことを指す場合もあります。
- write an obituary (死亡記事を書く)
- publish an obituary (死亡記事を掲載する)
- obituary notice (死亡告知)
- newspaper obituary (新聞の死亡記事)
- paid obituary (有料の死亡広告)
- edit an obituary (死亡記事を編集する)
- draft an obituary (死亡記事の下書きをする)
- submit an obituary (死亡記事を投稿する)
- obituary page/column (死亡記事欄)
- obituary writer (死亡記事を書く人)
- 語源:
- ラテン語「obitus(死、死去)」と関連があるとされます。
- ラテン語「obitus(死、死去)」と関連があるとされます。
- 歴史的背景:
- 新聞や雑誌が普及するに従って、亡くなった人を悼むための公式なお知らせとして「obituary」が広まったと言われています。
- 新聞や雑誌が普及するに従って、亡くなった人を悼むための公式なお知らせとして「obituary」が広まったと言われています。
- ニュアンスや注意点:
- 亡くなった方に対する追悼や尊敬を込めることが多いので、フォーマルで厳かな響きがあります。
- カジュアルな会話で「obituary」という単語を使うことはあまりありませんが、ニュースや新聞を読むときによく見かけます。
- 亡くなった方に対する追悼や尊敬を込めることが多いので、フォーマルで厳かな響きがあります。
- 可算・不可算
- 「obituary」は可算名詞で、具体的な記事や死亡告知文の一つ一つを数えるときに使われます(an obituary, two obituaries, etc.)。
- 使用シーン
- 新聞の死亡記事欄、追悼記事、フォーマルな文章など。
- 新聞の死亡記事欄、追悼記事、フォーマルな文章など。
- 一般的な構文例
- “(Someone) wrote/published an obituary for (deceased person).”
((誰か)が(故人)の死亡記事を執筆・掲載した)
- “(Someone) wrote/published an obituary for (deceased person).”
“I saw your grandfather’s obituary in the paper today and wanted to offer my condolences.”
(今日の新聞であなたのおじい様の死亡記事を見ました。お悔やみ申し上げます。)“I’m looking for the obituary section; I heard someone familiar passed away.”
(死亡記事欄を探しているんです。知っている方が亡くなったと聞いて…)“He kept a copy of the obituary as a remembrance.”
(彼は記念として、その死亡記事のコピーを取っておいた。)“Our public relations team prepared an obituary for the former CEO.”
(広報部が前CEOの死亡記事を用意しました。)“Could you confirm the details before we publish the obituary in the company newsletter?”
(社内報に死亡記事を掲載する前に、詳細を確認していただけますか?)“We need to make sure the obituary reflects his major accomplishments accurately.”
(死亡記事が彼の主要な業績を正確に反映するようにしなくてはなりません。)“The historian analyzed newspaper obituaries to study social attitudes toward the elderly.”
(歴史学者は、高齢者に対する社会的な考え方を研究するために新聞の死亡記事を分析した。)“Obituaries often provide insights into cultural perceptions of life and death.”
(死亡記事は、人生や死に対する文化的な認識を知る手がかりを与えてくれることが多い。)“In her dissertation, she cited obituaries to illustrate changing family structures.”
(彼女の論文では、家族構造の変化を示すために死亡記事を引用していた。)- death notice
- (死亡告知): 死亡を広く知らせる点では同じですが、比較的形式的な文芸的要素の少ない告知を指すことが多い。
- (死亡告知): 死亡を広く知らせる点では同じですが、比較的形式的な文芸的要素の少ない告知を指すことが多い。
- eulogy
- (追悼文・追悼演説): 葬儀などで故人をしのぶために読むスピーチや文だが、記事というよりはスピーチや式典の文脈で使われる。
- (追悼文・追悼演説): 葬儀などで故人をしのぶために読むスピーチや文だが、記事というよりはスピーチや式典の文脈で使われる。
- tribute
- (賛辞、敬意): 故人への感謝や尊敬の念を示す言葉や行為を指す。必ずしも死亡告知とは限らない。
- (賛辞、敬意): 故人への感謝や尊敬の念を示す言葉や行為を指す。必ずしも死亡告知とは限らない。
- birth announcement
- (誕生のお知らせ): 亡くなったことを知らせる「obituary」とは真逆で、新たな生命の誕生を知らせるもの。
- 発音記号(IPA): /əˈbɪtʃuːˌɛri/
- アクセント: 第2音節「-bit-」に強勢が置かれます。
- アメリカ英語とイギリス英語
- 大きな違いはありませんが、イギリス英語では /bə-/ の部分が少し曖昧母音気味に発音されることもあります。
- 大きな違いはありませんが、イギリス英語では /bə-/ の部分が少し曖昧母音気味に発音されることもあります。
- よくある発音ミス
- “obi” の部分を /oʊ/ ではなく /ɒ/ としてしまう人がいるので要注意です。
- “obi” の部分を /oʊ/ ではなく /ɒ/ としてしまう人がいるので要注意です。
- スペルミス: “obtiuary” や “obituaryy” など、スペルを誤る例が見られます。
- 同音異義語との混同: 目立った同音異義語はありませんが、“habitual” など似た綴りの単語と視覚的に混同しやすい場合があります。
- 試験対策: 新聞記事に関する読解問題で目にすることがある単語です。TOEICなどではあまり頻出ではありませんが、新聞・雑誌の記事を引用するテーマで出題される場合に備えておくとよいでしょう。
- 語源をイメージ: 「obit=死」と思い出しておくと、「obituary=“死に関する書きもの”」と覚えやすいです。
- 新聞から連想: 新聞の「死亡記事欄」のイメージを頭に浮かべることで、関連する場面が具体的になります。
- スペルのポイント: 「obi-」の後に「tu」ではなく「tuar」が続くところで注意(“obi-tu-ary”)。
- テクニック: フォーマル・公的な文脈でのみ使うという点に注目することで、ニュアンスの違いも覚えやすくなります。
- 英語の意味: A male police officer.
- 日本語の意味: 男性の警官。
- こういう場面で使われる: 主に男性の警察官を指し示す単語です。現在は性別を限定しない “police officer” と表現することが一般的ですが、「policeman」は依然として使われることがあります。やや古めの響きや、性別を強調する文脈で登場することがあります。
- 単数形: policeman
- 複数形: policemen
- 「police」(名詞/動詞/形容詞的用法もあり) :例 “the police” (警察全般を指す・複数扱い) や “to police an area” (管轄する/取り締まる) など
- 「policing」(動名詞/形容詞) :“policing policy” (警察による取り締まり政策) など
- 「policeman」の中には明確な接頭語や接尾語はありませんが、
- “police” (警察) + “man” (男性) の組み合わせとして理解できます。
- police officer: 性別を問わない警察官
- policewoman: 女性の警官
- policing: 治安維持、警備活動
- call the policeman(警官を呼ぶ)
- ask a policeman for directions(警官に道を尋ねる)
- the policeman on duty(当番の警官)
- a policeman’s badge(警官のバッジ)
- a policeman’s uniform(警官の制服)
- approach the policeman(警官に近づく)
- the policeman arrested the suspect(警官が容疑者を逮捕した)
- the policeman patrolled the streets(警官が街を巡回した)
- a friendly policeman(親切な警官)
- a policeman waved traffic through(警官が交通を整理する)
- 「policeman」は “police” (警察) + “man” (男) から構成されており、言葉の通り「男性の警察官」を示します。
- 19世紀後半から 20世紀にかけて広く使われるようになりましたが、近年はジェンダー中立的な用語として “police officer” が主に使われます。
- 現在では “policeman” と言うと男性しかイメージしないため、特に公的な文書や日常会話でも “police officer” と言うほうが望ましくなる場合が多いです。
- “policeman” はやや古風な響きがあり、口語・文章どちらでも性別を強調したいときに使われることがあります。
- 可算名詞: a policeman, two policemen
- “policeman” は主語や目的語として使われやすく、例えば “The policeman helped me” のように、助けてくれた人が男性警官であることを強調する際に使います。
- “A policeman pulled me over.”(警官が私を車で止めた)
- “He turned out to be a policeman undercover.”(実は潜入捜査中の警官だった)
- “She asked the nearest policeman for help.”(彼女は近くにいた警官に助けを求めた)
- 書き言葉・話し言葉の両方で使えますが、現代では “police officer” のほうがフォーマルかつジェンダーニュートラルです。
- “I asked a policeman for directions, and he was really kind.”
(警官に道を尋ねたら、とても親切だったよ。) - “A policeman stopped me for speeding.”
(スピード違反で警官に止められちゃった。) - “Have you seen a policeman around here? I need some help.”
(この辺りで警官を見かけましたか?ちょっと助けが必要なんです。) - “The event organizers coordinated with a policeman to manage the crowd.”
(イベントの主催者は群衆を管理するために警官と調整を行った。) - “A policeman came to our office to discuss security measures.”
(警官がオフィスに来て、セキュリティ対策について話し合った。) - “Contact a policeman immediately if something suspicious occurs outside the venue.”
(会場の外で何か不審なことが起きたら、すぐに警官へ連絡してください。) - “A research paper investigated the stress levels of a policeman in urban areas.”
(ある研究論文では、市街地に勤務する警官のストレスレベルを調査していた。) - “The municipal council invited a veteran policeman to speak on community policing.”
(市議会はコミュニティ・ポリシングについて話をしてもらうため、経験豊富な警官を招いた。) - “A historian analyzed the changing role of the policeman in 19th-century London.”
(歴史家が19世紀のロンドンにおける警官の役割の変化を分析した。) - police officer(警察官)
- 性別を問わず使用できる現代的かつ正式な言い方。
- 性別を問わず使用できる現代的かつ正式な言い方。
- officer(警察官/消防士/軍人など、階級を持つ公務員にも広く使う)
- cop(俗語表現:警官)
- くだけた口語表現で、親しみやすいけれどややカジュアル。
- くだけた口語表現で、親しみやすいけれどややカジュアル。
- criminal(犯罪者)
- suspect(容疑者)
- civilian(民間人)
- 発音記号(IPA):
- アメリカ英語: /pəˈliːs.mən/
- イギリス英語: /pəˈliːs.mən/
- アメリカ英語: /pəˈliːs.mən/
- アクセントの位置: “po*LICE*man” の “LICE” の部分に強勢があります。
- アメリカ英語とイギリス英語の違い:
- 大きな違いはほぼありませんが、アクセントや母音の伸ばし方にわずかな差があります。
- 大きな違いはほぼありませんが、アクセントや母音の伸ばし方にわずかな差があります。
- よくある発音の間違い:
- 最初の “po” の部分を強く読む、または “police” の “i” を短く読むなどの誤りに注意。
- スペルミス: “policeman” の “e” を抜かして “policman” と書いてしまう。
- 同音異義語との混同: 特別な同音異義語はありませんが、「polish」と混同しないように注意。
- 試験対策: TOEIC や英検などで、ジェンダーニュートラル表現を推奨する近年の傾向からは “police officer” が頻出になる可能性ありますが、「policeman」も単語としてはテストに出てくることがあります。
- “police + man” という組み合わせをイメージして覚えると、すぐに意味が回想できます。
- 昔の映画やドラマでよく登場する「お巡りさん」をイメージすると “policeman” の単語感覚が残りやすいです。
- ジェンダーニュートラルな言い方 “police officer” を同時に覚えておくと、現在の英語表現として使い勝手がよいでしょう。
trait
trait
解説
〈C〉《かたく》 (性格・身体上の) 特徴, 特性, 性質
trait
1. 基本情報と概要
単語: trait
品詞: 名詞 (noun)
意味 (英語): a distinguishing quality or characteristic
意味 (日本語): 「特徴」や「特性」といった意味を示します。
「trait」は主に、人や物などの持つ特徴・特質について言及するときに使われる単語です。たとえば「性格的な特徴」や「遺伝子的な特質」など、対象を定義づける重要な要素を表現します。
活用形:
他の品詞に変化した例:
CEFR レベルの目安: B2(中上級)
2. 語構成と詳細な意味
語構成:
派生語や類縁語:
よく使われるコロケーション(共起表現)や関連フレーズ10選:
3. 語源とニュアンス
語源:
ニュアンス・使用上の注意点:
4. 文法的な特徴と構文
一般的な構文例:
イディオム: 特に“trait”を中心としたイディオムは多くはありませんが、「character trait」や「personality trait」は非常に頻繁に使われるフレーズです。
5. 実例と例文
(1) 日常会話
(2) ビジネス
(3) 学術・専門的な文脈
6. 類義語・反意語と比較
類義語 (Synonyms)
反意語 (Antonyms)
7. 発音とアクセントの特徴
8. 学習上の注意点・よくある間違い
9. 記憶に残るヒントやイメージ
以上が、名詞「trait」の詳細解説となります。人や物が持つ特徴・特性を表す単語として、日常から学術的な場面まで幅広く使われるため、ぜひ覚えて活用してみてください。
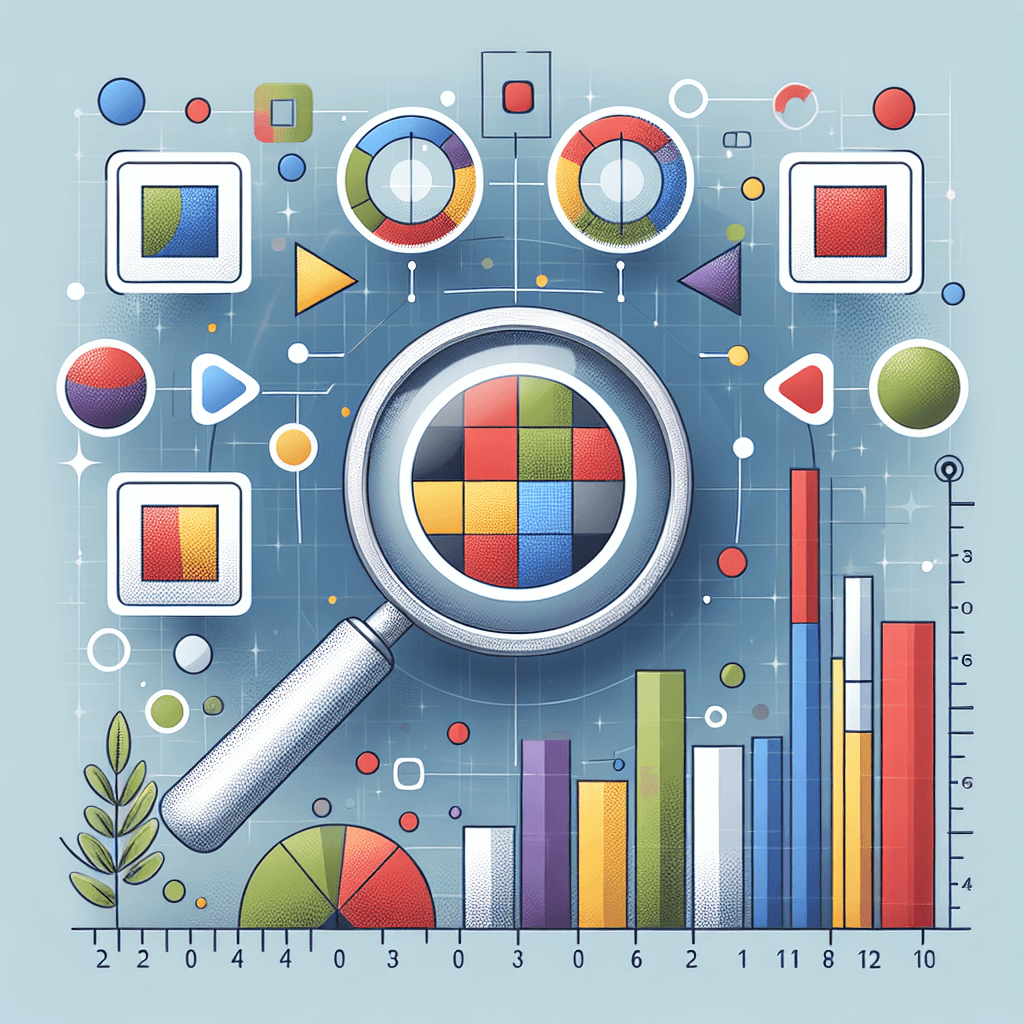
特性,特質,特色
【形】《...より》下位の 《to ...》 / 従属的な / 【名/C】従属するもの, 部下 / 【動/他】《...より》...を下位におく, 《...に》...を従属させる《to ...》
subordinate
subordinate
解説
【形】《...より》下位の 《to ...》 / 従属的な / 【名/C】従属するもの, 部下 / 【動/他】《...より》...を下位におく, 《...に》...を従属させる《to ...》
subordinate
【形】《...より》下位の 《to ...》 / 従属的な / 【名/C】従属するもの, 部下 / 【動/他】《...より》...を下位におく, 《...に》...を従属させる《to ...》
1. 基本情報と概要
単語: subordinate
品詞: 形容詞 / 名詞 / 動詞
活用形:
他の品詞形:
CEFRレベルの目安: B2(中上級)
2. 語構成と詳細な意味
接頭語・接尾語・語幹
これらが合わさって、「下位に位置づける」「従属している」という意味を成しています。
派生語や類縁語
よく使われるコロケーション(共起表現)10選
3. 語源とニュアンス
語源
ラテン語の “subordinare” からきており、
という組み合わせから成り立ちます。「下位に配置する」「何かの下に置く」という感覚が元にあります。
ニュアンス・使用上の注意
4. 文法的な特徴と構文
イディオム・慣用的な構文
5. 実例と例文
日常会話
ビジネス
学術的な文脈
6. 類義語・反意語と比較
類義語
反意語
7. 発音とアクセントの特徴
8. 学習上の注意点・よくある間違い
9. 記憶に残るヒントやイメージ
以上が “subordinate” の詳細解説です。ビジネスや組織内の上下関係にまつわる表現としてはもちろん、文法(従属節)や社会階層の話題でも活躍する単語です。上司と部下の関係、何かを別のことに従属させるイメージなど、文脈によって使い分けてみてください。

(…より)下位の,下級の《+to+名》
従属的な,捕助的な
従属する人(物);部下,属官
(…より)…‘を'下位におく,(…に)…‘を'従属させる《+名+to+名》
【動/自】《雑誌などを》定期購読する《to, for ...》 / 《...に》加入する, 申し込む《to ...》 / 《…に》寄付する, 出資する《to, for ...》 / 《…に》同意する,賛成する《to ...》 / 【動/他】《…に》〈金〉を寄付する《to ...》 / 〈書類〉に署名する
subscribe
subscribe
解説
【動/自】《雑誌などを》定期購読する《to, for ...》 / 《...に》加入する, 申し込む《to ...》 / 《…に》寄付する, 出資する《to, for ...》 / 《…に》同意する,賛成する《to ...》 / 【動/他】《…に》〈金〉を寄付する《to ...》 / 〈書類〉に署名する
subscribe
【動/自】《雑誌などを》定期購読する《to, for ...》 / 《...に》加入する, 申し込む《to ...》 / 《…に》寄付する, 出資する《to, for ...》 / 《…に》同意する,賛成する《to ...》 / 【動/他】《…に》〈金〉を寄付する《to ...》 / 〈書類〉に署名する
1. 基本情報と概要
単語: subscribe
品詞: 動詞 (verb)
英語の意味:
日本語の意味:
「雑誌を定期購読したり、YouTubeチャンネルに登録したりする時に使われる動詞です。また、意見に同意する、賛成するというニュアンスでも使われる場合があります。誰かの主張に ‘I subscribe to that idea.’ のように表現します。」
活用形:
他の品詞形:
CEFRレベル (目安): B2 (中上級)
日常生活だけでなくビジネスの文脈でも使われる場面がある単語で、ある程度英語表現に慣れてきた方が把握しておくと便利です。
2. 語構成と詳細な意味
“subscribe” は本来、「文書の下にサインを書く」→「署名して賛成や同意を表明する」→「定期購読や加入を申し込む」という流れで意味が広がってきました。
よく使われるコロケーション(共起表現)10選
3. 語源とニュアンス
4. 文法的な特徴と構文
5. 実例と例文
日常会話での例文
ビジネスでの例文
学術的/フォーマルな文脈での例文
6. 類義語・反意語と比較
類義語 (Synonyms)
「subscribe」は、「サインアップ」や「登録する」という意味だけでなく、「考え方に賛同する」という範囲までカバーする点が特徴です。
反意語 (Antonyms)
7. 発音とアクセントの特徴
8. 学習上の注意点・よくある間違い
9. 記憶に残るヒントやイメージ
以上が “subscribe” の詳細な解説です。勉強や日常会話・ビジネス・学術場面などでぜひ活用してみてください。
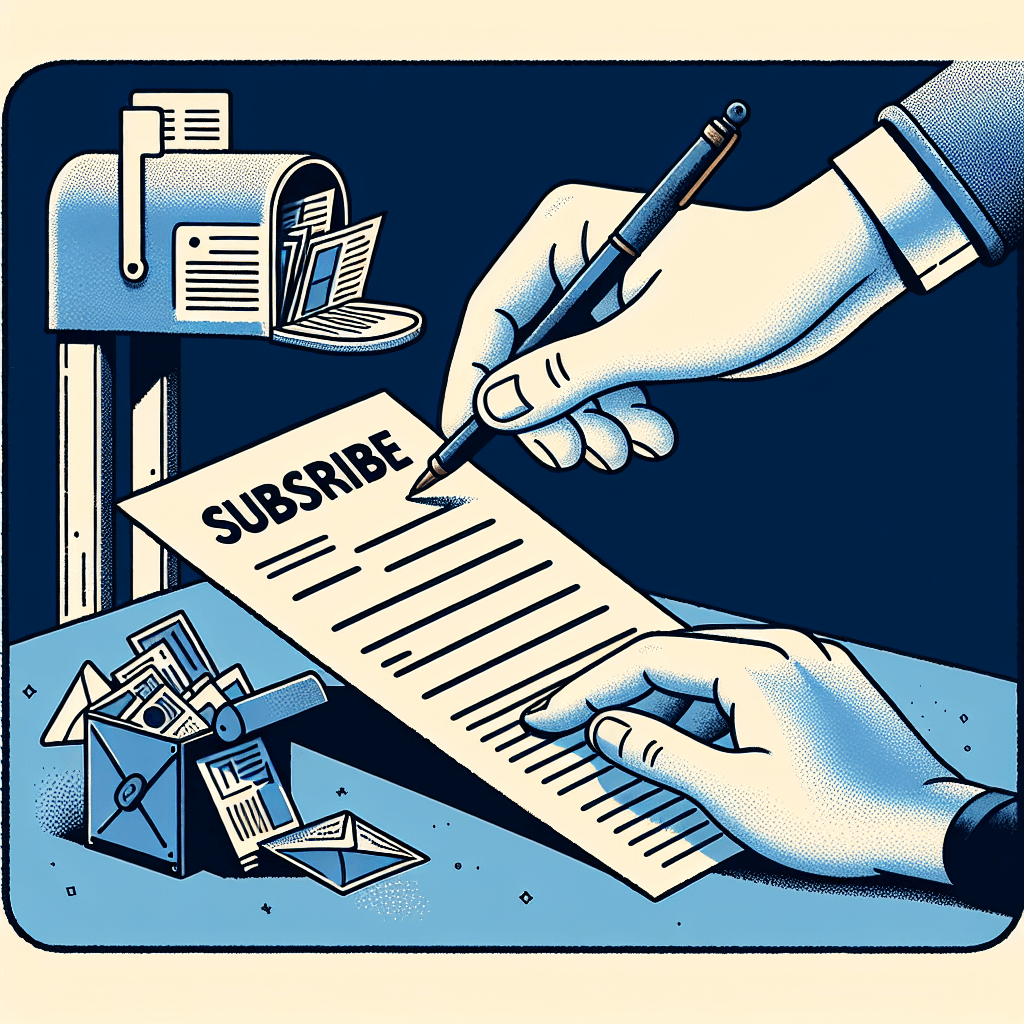
(雑誌・切符などを)予約する《+to(for)+名》
(…に)寄付(出資)を約束する,寄付(出資)する《+to(for)+名》,(…を)寄付する《+for+名》
(書類などの終りに)署名する《+to+名》
(…に)同意する,賛成する《+to+名》
(…に)〈金〉‘の'寄付(支払い)を約束する,‘を'寄付する,支払う《+名+to(for)+名》
〈書類〉‘に'署名する;〈自分の名前〉‘を'書く(sign)
publish
publish
解説
...を出版する, を発行する / (作家など) の作品を出版する / を公表する / 出版する, 発行する
publish
1. 基本情報と概要
単語: publish
品詞: 動詞 (他動詞が主だが、文脈によっては自動詞的にも使われることがある)
意味(英語): to make content (such as books, articles, or information) available to the public
意味(日本語): 書籍や記事などの内容を公に公開・刊行すること
「publish」は、書籍や新聞、論文などを「発行する」「公にする」というニュアンスで使われる動詞です。文章・情報を世の中に送り出すような場面でよく用いられます。
活用形:
他の品詞形:
CEFRレベルの目安: B2(中上級)
・B2(中上級): 日常会話はおおむねできて、やや専門的な内容にも対応可能になるレベル。大学生や社会人レベルでよく使う語。
2. 語構成と詳細な意味
語構成
詳細な意味
よく使われるコロケーション(共起表現)10選
3. 語源とニュアンス
“publish” はラテン語の “publicare”(公にする)や “publicus”(公共の)に由来します。もともとは「公表する」「公共の場に出す」という意味合いが語源となっています。
ニュアンス・使用時の注意点
4. 文法的な特徴と構文
5. 実例と例文
以下では、日常会話、ビジネス、そして学術的な場面のそれぞれ3例ずつ示します。
日常会話での例文
ビジネスでの例文
学術的な文脈での例文
6. 類義語・反意語と比較
類義語 (Synonyms)
反意語 (Antonyms)
7. 発音とアクセントの特徴
8. 学習上の注意点・よくある間違い
9. 記憶に残るヒントやイメージ
以上が “publish” の詳細解説です。ビジネスや学術、日常会話まで幅広いシーンで使える便利な単語なので、例文やコロケーションとともにぜひ覚えておいてください。

〈本・雑誌など〉‘を'出版する,発行する;〈作家など〉‘の'作品を出版する
…‘を'一般に知らせる,公表する
出版する,発行する
accumulate
accumulate
解説
を蓄積する,ためる / 蓄積する,たまる
accumulate
1. 基本情報と概要
単語: accumulate
品詞: 動詞 (他動詞・自動詞)
英語での意味:
日本語での意味:
活用形:
他の品詞例:
CEFRレベルの目安:
2. 語構成と詳細な意味
語構成:
関連語と派生語
よく使われるコロケーション・フレーズ(10個)
3. 語源とニュアンス
語源:
ニュアンス:
4. 文法的な特徴と構文
一般的な構文やイディオム
5. 実例と例文
日常会話 (3例)
ビジネス (3例)
学術的な文脈 (3例)
6. 類義語・反意語と比較
類義語
反意語
7. 発音とアクセントの特徴
8. 学習上の注意点・よくある間違い
9. 記憶に残るヒントやイメージ
以上が「accumulate」の詳細解説です。時間をかけて物や情報が粘り強く集まるイメージを持って、さまざまな文脈で使ってみてください。
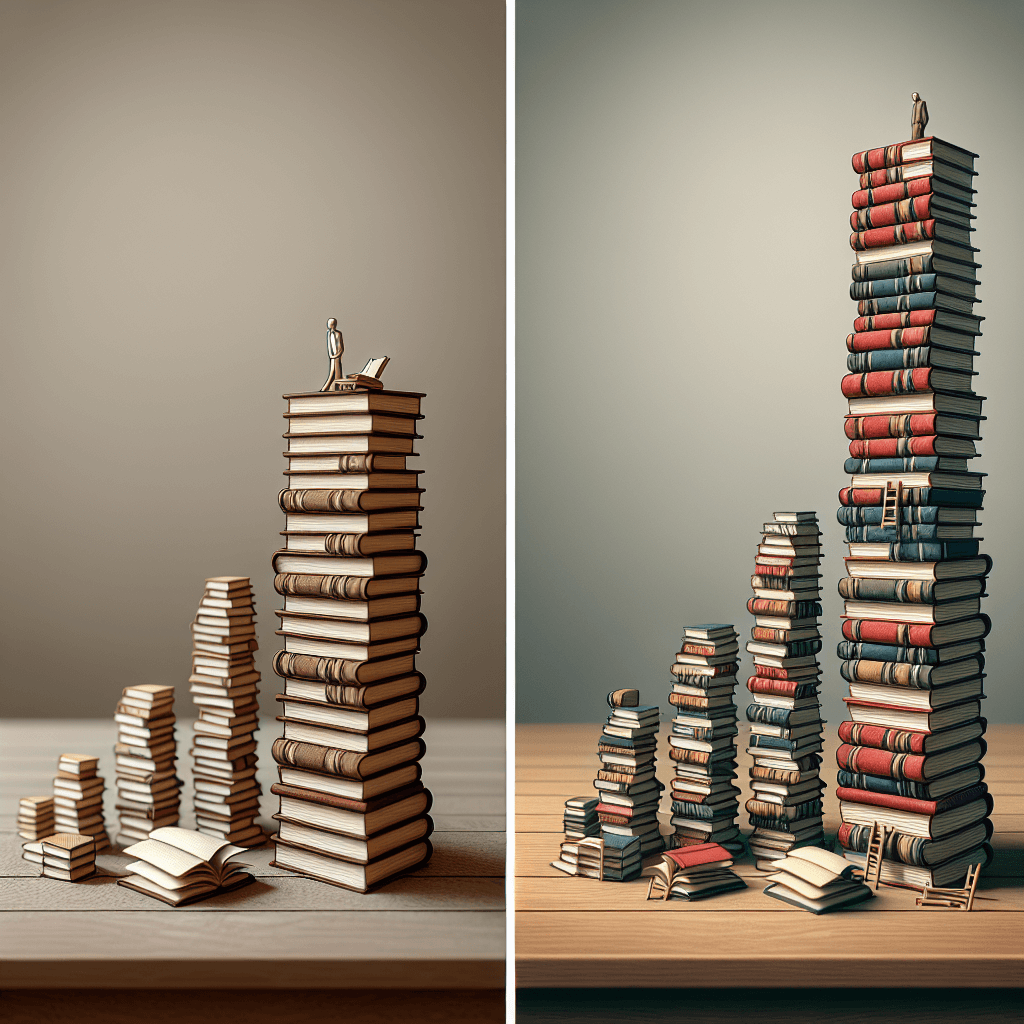
…'を'蓄積する,ためる
たまる,ふえる
depart
depart
解説
《文》《…から》(遠くへ)立ち走る, 出発する《from ...》 / 《通常のことから》はずれる,変わる《from ...》
depart
1. 基本情報と概要
単語: depart
品詞: 動詞 (Verb)
活用形:
英語での意味:
“to leave a place, especially to start a journey” (ある場所を離れる、特に旅を始める)
日本語での意味:
「出発する」「離れる」「旅立つ」のような意味合いを持ちます。列車や飛行機が出発するときや、人がどこかへ向かって旅立つときに使います。比較的フォーマルな響きがあり、文書やアナウンスなどでよく使われるイメージの単語です。
CEFRレベル: B2(中上級)
他の品詞になった例:
2. 語構成と詳細な意味
接頭語: “de-”
語幹: “part”
よく使われるコロケーション(共起表現)10選
3. 語源とニュアンス
語源:
ニュアンスや使用時の注意点:
4. 文法的な特徴と構文
使用シーン
イディオム等:
5. 実例と例文
A) 日常会話での例文 (3つ)
B) ビジネスでの例文 (3つ)
C) 学術的・フォーマルな文脈での例文 (3つ)
6. 類義語・反意語と比較
類義語 (Synonyms)
反意語 (Antonyms)
7. 発音とアクセントの特徴
発音記号 (IPA)
強勢(アクセント)の位置: “de-PART” のように第二音節「part」に強勢があります。
よくある混乱:
8. 学習上の注意点・よくある間違い
9. 記憶に残るヒントやイメージ
以上が、動詞 “depart” の詳細な解説です。フォーマルな場面や時刻表、会議や出張の予定などに関連付けて覚えると、使い方が定着しやすくなります。

(通常のことから)はずれる,変わる《+from+名》
《文》(…から)(遠くへ)立ち走る,出発する《+from+名》
hydrogen
hydrogen
解説
水素(化学記号はH)
hydrogen
「hydrogen」の解説
1. 基本情報と概要
英語表記: hydrogen
品詞: 名詞 (不可算名詞)
意味
「水素」は科学の分野でよく出てくる単語です。燃料電池や化学反応に関係する場面で使われます。英語圏では日常生活でそこまで頻繁に出る単語ではありませんが、近年クリーンエネルギーとして注目されているため、ニュースや科学記事などで目にする機会があります。
活用形
他の品詞形
CEFRレベルの目安
2. 語構成と詳細な意味
語構成
この2つが合わさって「水を生じさせるもの」という意味を持ちます。実際には「水が生成される」というところから名付けられており、水素が酸素と結合すると水になることにちなんでいます。
関連・派生語
コロケーション(共起表現)10選
3. 語源とニュアンス
語源
ニュアンス・使用時の注意
4. 文法的な特徴と構文
一般的な構文・イディオム
5. 実例と例文
日常会話での例文
ビジネスシーンでの例文
学術的な文脈での例文
6. 類義語・反意語と比較
類義語
※「hydrogen」と意味が近い単語はあまりありませんが、燃料系単語(gas, propane, etc.)と一緒に並びやすいです。
反意語
7. 発音とアクセントの特徴
8. 学習上の注意点・よくある間違い
9. 記憶に残るヒントやイメージ
以上が「hydrogen」の詳細な解説です。化学や環境関連の文章によく出てくるので、ニュースや科学記事などで見かけたときに参考にしてください。

水素(化学記号はH)
probe
probe
解説
探査器 / 探求 / 問題点 / 探測器 / 調査
probe
1. 基本情報と概要
単語: probe
品詞: 名詞 (動詞としても使われる)
CEFRレベルの目安: B2(中上級)
英語での意味:
日本語での意味:
活用形
他の品詞への派生
2. 語構成と詳細な意味
関連語や派生語
よく使われるコロケーション(10個)
3. 語源とニュアンス
語源: ラテン語の「試す」「証明する」を意味する “probare” に由来します。同じ語源を持つ単語に “proof” (証拠) や “probable” (ありそうな) があります。
歴史的に「試験する」「調べる」という意味が強く、現代では科学技術や事件調査など幅広い文脈で用いられます。
ニュアンスや使い方:
4. 文法的な特徴と構文
一般的な構文・イディオム例
5. 実例と例文
A. 日常会話での例 (3つ)
B. ビジネスシーンでの例 (3つ)
C. 学術的・専門的な文脈での例 (3つ)
6. 類義語・反意語と比較
類義語
“probe” は「機械を使って調べる」「根掘り葉掘り追及する」といったニュアンスが強い点が他と異なる特徴です。
反意語
7. 発音とアクセントの特徴
8. 学習上の注意点・よくある間違い
9. 記憶に残るヒントやイメージ
以上が名詞 “probe” の詳細な解説です。科学的な文脈でよく登場する単語ですが、ビジネスや法的な場面でも「深掘り調査、探査に用いる道具/調査」というニュアンスで幅広く使われる便利な単語です。
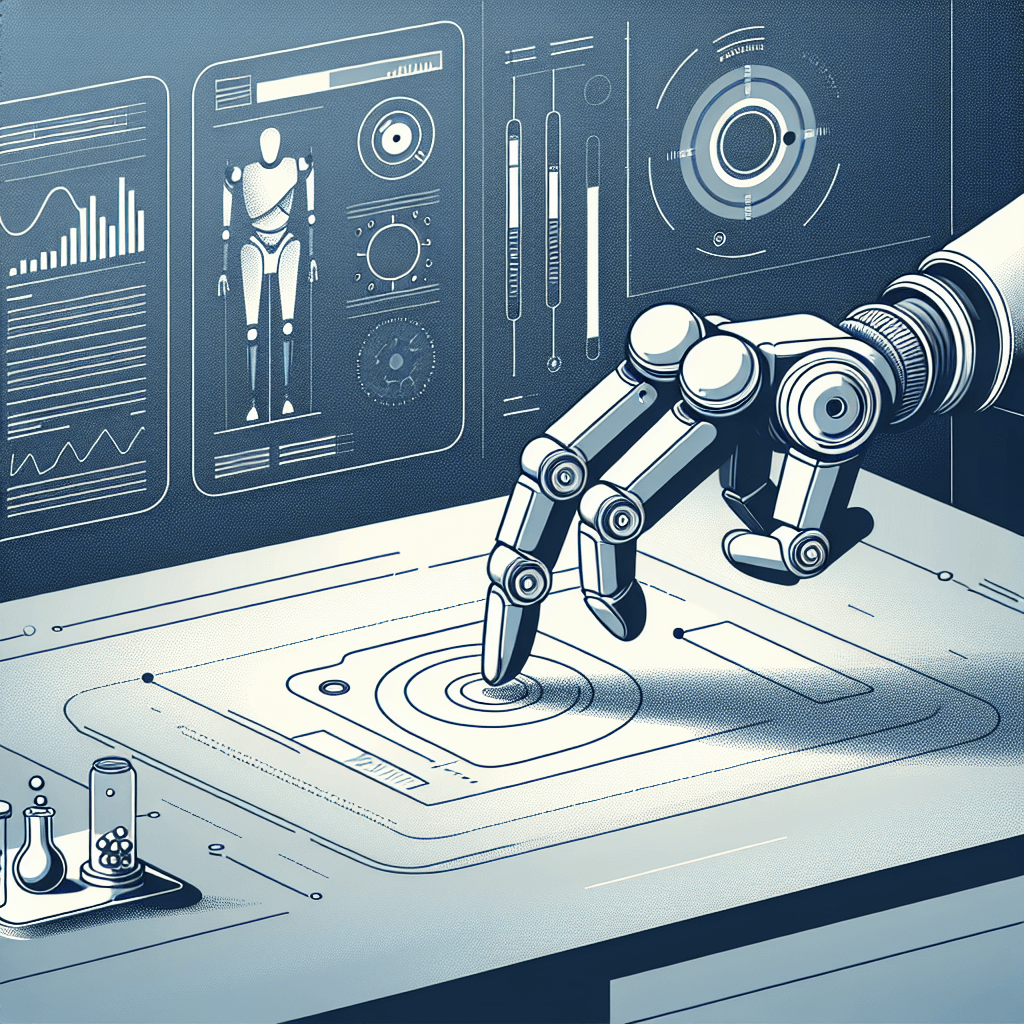
(傷の深さを調べる)さぐり針
(…を)厳密に調べること,精査《+into(for,at)+名》
(またspace probe)(ロケットの)宇宙探測機
obituary
obituary
解説
(新聞などの)死亡記事
obituary
1. 基本情報と概要
単語: obituary
品詞: 名詞 (英語では「obituary」という形で、複数形は「obituaries」)
意味(英語)
A notice of a person’s death, usually placed in a newspaper, with a short biography or summary of their life and achievements.
意味(日本語)
人が亡くなったことを知らせる告知文で、通常は新聞などに掲載されます。その人の経歴や功績、家族へのお知らせなどが簡単に書かれます。
「亡くなったことを敬意をもって通知する文書」で、比較的フォーマルなニュアンスがあります。
活用形
名詞以外での用法はあまり一般的ではありませんが、「obituary notice(死亡告知)」のように形容詞的に使われる表現もあります。
CEFRレベルの目安
2. 語構成と詳細な意味
「obituary」はラテン語の “obitus(死、死亡)” に由来するとされ、「死に関連する知らせ」を表します。
関連する派生語・類縁語
よく使われるコロケーションや関連フレーズ(10例)
3. 語源とニュアンス
4. 文法的な特徴と構文
5. 実例と例文
日常会話での例文(3例)
ビジネスシーンでの例文(3例)
学術的な文脈(3例)
6. 類義語・反意語と比較
類義語
反意語
7. 発音とアクセントの特徴
8. 学習上の注意点・よくある間違い
9. 記憶に残るヒントやイメージ
以上が、obituary(名詞)の詳細解説です。死亡時の告知記事を示すフォーマルな語なので、新聞や雑誌の文脈でよく出てきます。フォーマルさと敬意を払うニュアンスを含んでいるため、使用時には場面に合った言葉遣いが求められる点を意識してください。
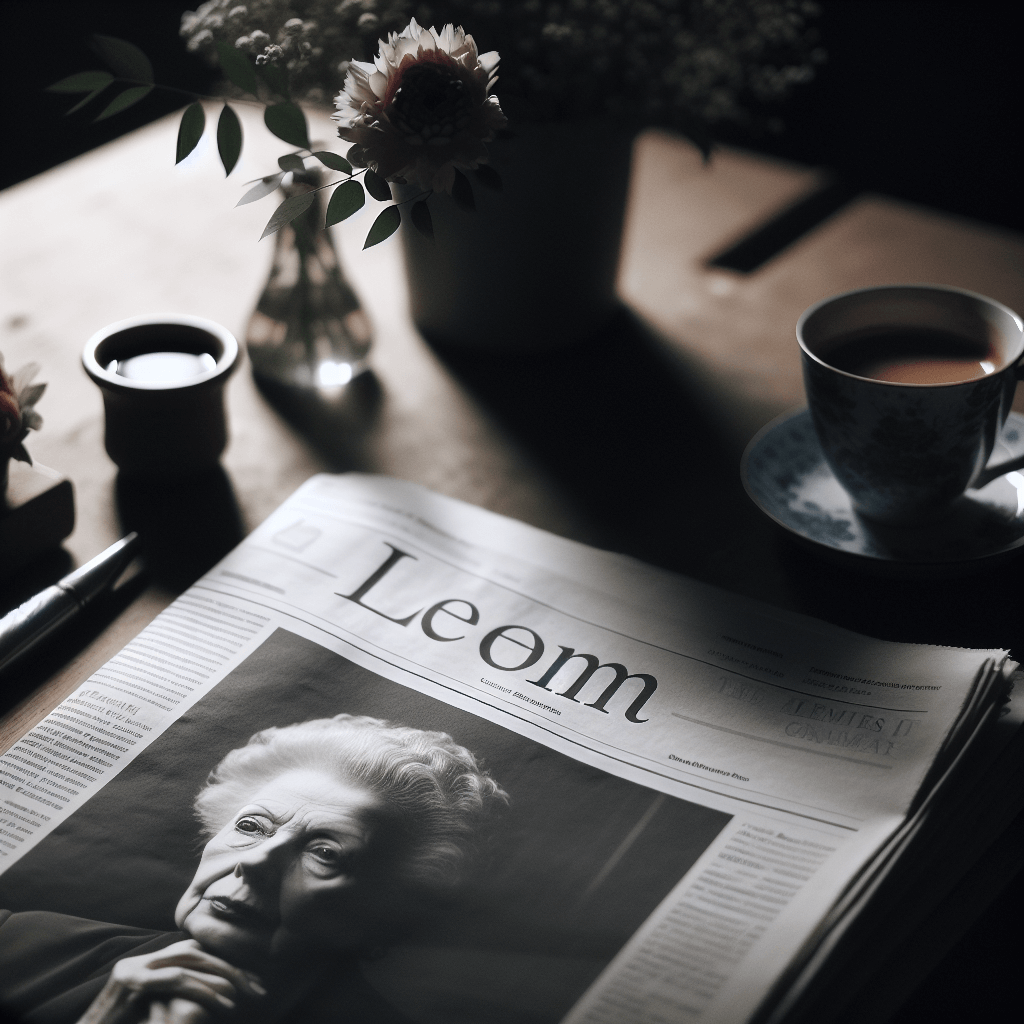
(新聞などの)死亡記事
policeman
policeman
解説
〈C〉警官, 巡査
policeman
1. 基本情報と概要
単語: policeman
品詞: 名詞 (可算名詞)
CEFRレベルの目安: A2(初級)
活用形:
他の品詞形:
2. 語構成と詳細な意味
語構成:
関連性・派生語:
よく使われるコロケーション(共起表現)や関連フレーズ(10個)
3. 語源とニュアンス
語源:
使用時の注意点とニュアンス:
4. 文法的な特徴と構文
よくある構文やイディオム例:
フォーマル/カジュアル:
5. 実例と例文
日常会話での例文(3つ)
ビジネスシーンでの例文(3つ)
学術的/公的な文脈での例文(3つ)
6. 類義語・反意語と比較
類義語:
反意語:(「警官」の反意語は明示的にはありませんが、職業や立場で対比させる場合)
上記は職務上の立場が対立するときに、例として取り上げられます。
7. 発音とアクセントの特徴
8. 学習上の注意点・よくある間違い
9. 記憶に残るヒントやイメージ
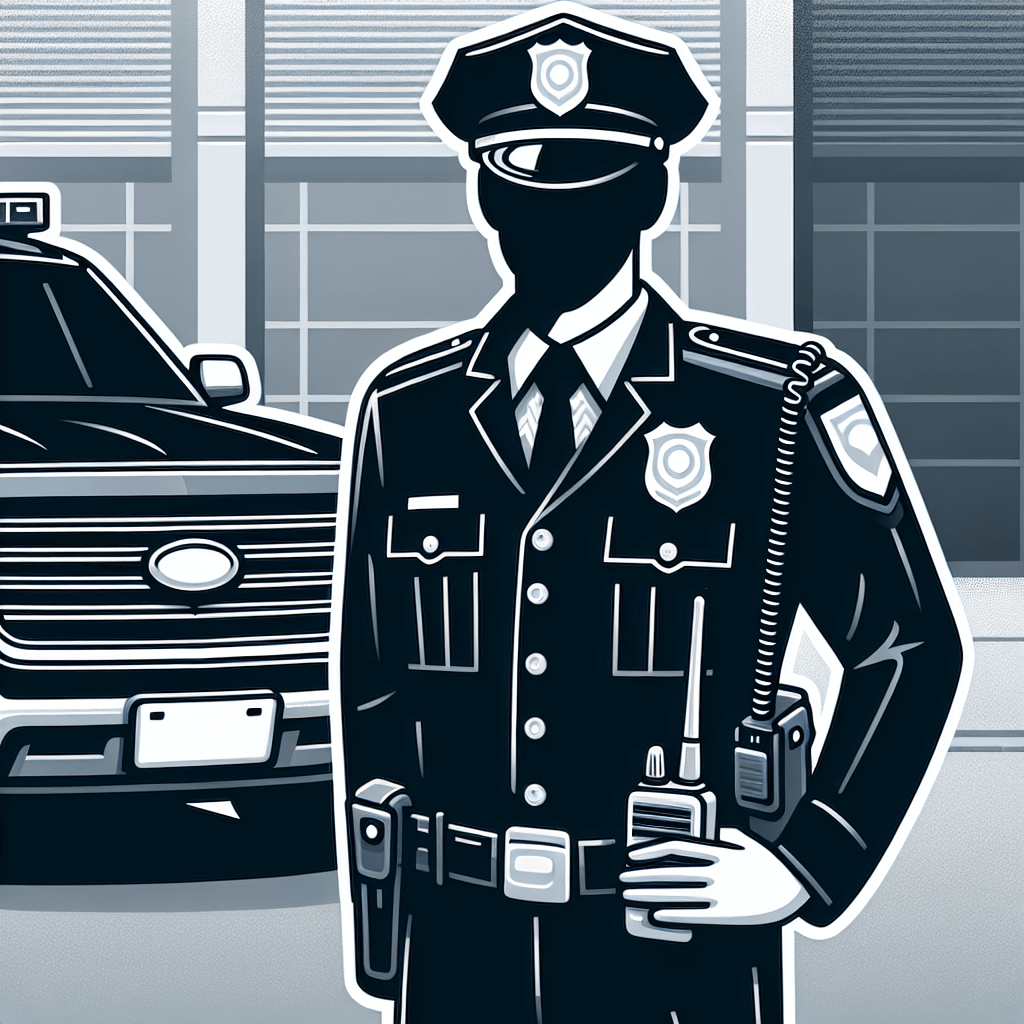
警官,巡査
loading!!

ビジネス英単語(BSL)

ビジネスに頻出の英単語です。
基礎英単語と合わせて覚えることで、ビジネス英文に含まれる英単語の9割をカバーします。
この英単語を覚えるだけで、英文の9割は読めるようになるという話【NGSL,NAWL,TSL,BSL】
外部リンク
キー操作
最初の問題を選択する:
Ctrl + Enter
解説を見る:Ctrl + G
フィードバックを閉じる:Esc
問題選択時
解答する:Enter
選択肢を選ぶ:↓ or ↑
問題の読み上げ:Ctrl + K
ヒントを見る: Ctrl + M
スキップする: Ctrl + Y





