最終更新日
:2025/01/27
is to
IPA(発音記号)
解説
1. 基本情報と概要
単語(表現): is to
品詞: 助動詞的な役割(実際には “be” 動詞 + 不定詞 “to” の準助動詞的構文)
意味(英語・日本語)
- 英語: “is to” は “be to + 動詞の原形” という形で用いられ、「~することになっている」「~しなければならない」「もし~するならば」などの意味を表します。
- 日本語: 「~する予定・義務・指示」「もし~するためには」など。少しフォーマルな響きがあり、公的・正式な場面で使われます。
たとえば、「He is to leave tomorrow.」は「彼は明日出発することになっている」という意味になります。命令や義務を表す場合もあるので、文脈によって意味が変わることに注意してください。
活用形
- “is to” は、主語に合わせて “am to”, “are to” に形を変えます。主語の数や人称により “be” 動詞部分が変化します。
- I am to …
- You are to …
- He/She/It is to …
- We are to …
- They are to …
- I am to …
他の品詞になったときの例
- “be to” 構文は、厳密には「be」動詞(動詞) + 「to」不定詞ですが、派生形としては存在しません。代わりに意味の近い 「should」、「must」、「have to」 などの助動詞と比較されることが多いです。
CEFRレベル目安: B2(中上級)
- B2: 自分の専門分野であれば複雑な情報を処理でき、フォーマルな表現にも対応し始めるレベル
- “be to” の構文は会話にはそこまで頻出しないものの、ニュース記事や公的な文書などフォーマルな場で用いられることがあるため、B2 レベル前後で習得されやすいです。
2. 語構成と詳細な意味
接頭語・接尾語・語幹
- “is to” は「be + to + 動詞の原形」の一部であり、接頭語・接尾語の概念はありません。
- “be” 動詞の一つの形 (is) と、不定詞マーカー (to) が結びついています。
他の単語との関連性(派生語や類縁語)
- 意味合いが似ている助動詞表現: shall, should, must, have to, be supposed to, etc.
よく使われるコロケーションや関連フレーズ(10個)
- “He is to blame.”
- (彼に責任がある / 彼が悪いとされる)
- (彼に責任がある / 彼が悪いとされる)
- “She is to appear in court.”
- (彼女は法廷に出席することになっている)
- (彼女は法廷に出席することになっている)
- “We are to meet at noon.”
- (私たちは正午に会う予定だ)
- (私たちは正午に会う予定だ)
- “The team is to win the championship.”
- (そのチームは優勝するだろう / する予定だ)
- (そのチームは優勝するだろう / する予定だ)
- “This plan is to be completed by Friday.”
- (この計画は金曜日までに完成されることになっている)
- (この計画は金曜日までに完成されることになっている)
- “All students are to remain silent.”
- (すべての学生は静かにしていなければならない)
- (すべての学生は静かにしていなければならない)
- “If he is to succeed, he must work harder.”
- (もし彼が成功するつもりなら、もっと努力しなければならない)
- (もし彼が成功するつもりなら、もっと努力しなければならない)
- “No one is to leave the building.”
- (誰も建物を出てはならない)
- (誰も建物を出てはならない)
- “The president is to address the nation tonight.”
- (大統領は今夜、国民に向けて演説することになっている)
- (大統領は今夜、国民に向けて演説することになっている)
- “Everyone is to follow the guidelines.”
- (全員がガイドラインに従うことになっている)
3. 語源とニュアンス
語源
- “be to” 構文は中英語の時代頃から存在しており、当初は予定や運命などを示す表現として用いられました。
- 形式的・論理的な文章で「~すべき」「~になる運命にある」などのニュアンスを伝えるために使われてきました。
使用時の注意点や微妙なニュアンス
- 口語よりもやや文語的・フォーマルな響きがあります。
- 「義務」について触れる時は若干厳格で命令に近い印象を与える場合があります。
- 条件文 “If ~ is to …” の形で「もし~したいならば、~しなければならない」という含意を持ちます。
使われるシーン
- 新聞記事や公式発表(政府や企業の発表など)
- 議会や法廷のようなフォーマルな場面
- 文学作品や物語の冒頭でも、運命や必然性を示すのに使われる場合があります。
4. 文法的な特徴と構文
- 構文: “主語 + be(動詞変化) + to + 動詞の原形”
意味パターン:
- 命令・義務: “All visitors are to wear a badge.”
- 予定・運命: “He is to arrive at noon.”
- 条件: “If she is to succeed, she must practice more.”
- 命令・義務: “All visitors are to wear a badge.”
フォーマル度: 一般的にフォーマルまたはやや硬い表現
可算・不可算や他動詞・自動詞の区別:
- “is to” 自体は助動詞的表現なので、可算/不可算や他動詞/自動詞の区別は当てはまりません。
5. 実例と例文
日常会話(カジュアル)
- “I am to pick up my sister after school, so I can’t go to the movies now.”
- (学校のあと妹を迎えに行くことになっているから、映画には今行けないんだ。)
- (学校のあと妹を迎えに行くことになっているから、映画には今行けないんだ。)
- “We’re to help Mom with dinner tonight.”
- (今夜は夕食作りを手伝うことになっているんだ。)
- (今夜は夕食作りを手伝うことになっているんだ。)
- “He is to do the dishes today, and I’ll cook instead.”
- (彼は今日は食器を洗う当番で、代わりに僕が料理をするよ。)
ビジネス(フォーマル)
- “All employees are to submit their reports by Friday.”
- (すべての従業員は金曜日までに報告書を提出しなければなりません。)
- (すべての従業員は金曜日までに報告書を提出しなければなりません。)
- “The minister is to visit the factory next week.”
- (大臣は来週、その工場を訪問することになっています。)
- (大臣は来週、その工場を訪問することになっています。)
- “If our company is to remain competitive, we must innovate quickly.”
- (もし当社が競争力を維持するつもりなら、迅速にイノベーションを起こさなければなりません。)
学術的・公的な文脈
- “The new policy is to be implemented nationwide.”
- (新たな政策は全国的に施行される予定です。)
- (新たな政策は全国的に施行される予定です。)
- “If the research is to reach conclusive results, further funding is necessary.”
- (この研究が決定的な結果を得るためには、さらなる資金が必要です。)
- (この研究が決定的な結果を得るためには、さらなる資金が必要です。)
- “He is to present his findings at the international conference.”
- (彼は国際会議で研究成果を発表することになっています。)
6. 類義語・反意語と比較
類義語
- “should” (~すべきだ)
- 「道徳的・推奨的」なニュアンスが強く、硬さは “is to” よりもやや弱い。
- 「道徳的・推奨的」なニュアンスが強く、硬さは “is to” よりもやや弱い。
- “must” (~しなければならない)
- 「強制・絶対的必要性」が強い。
- 「強制・絶対的必要性」が強い。
- “have to” (~しなければならない)
- 「外的要因による義務」を伝えるカジュアルな表現。
- 「外的要因による義務」を伝えるカジュアルな表現。
- “be supposed to” (~することになっている)
- 「暗黙の約束」や「常識的にそうである」ニュアンスがある。
- 「暗黙の約束」や「常識的にそうである」ニュアンスがある。
- “shall” (~しましょう / ~するべきだ)
- 提案や法的な強い命令表現としても使われる。
反意語
- “is not to” と否定形で用いられることがあり、「~してはならない」「~することはない」といった禁止や不許可を示す場合もあります。完全に反意語というよりは、否定形で義務や予定を打ち消す形です。
7. 発音とアクセントの特徴
発音記号(IPA):
- “is” → /ɪz/ または /ɪs/(地域差)
- “to” → /tuː/ または弱形で /tə/ (文中でしばしば弱まる)
- “is” → /ɪz/ または /ɪs/(地域差)
アクセントの位置:
- “is” に強いアクセントはありません。文脈上、主節で意味を出したい “to + 動詞の原形” 部分が意識されやすい。
- “is” に強いアクセントはありません。文脈上、主節で意味を出したい “to + 動詞の原形” 部分が意識されやすい。
アメリカ英語とイギリス英語の違い:
- 大きな違いはほとんどありませんが、/tu/ と /tə/(弱形)の使い方にやや差が見られる場合があります。
- 大きな違いはほとんどありませんが、/tu/ と /tə/(弱形)の使い方にやや差が見られる場合があります。
よくある発音の間違い:
- “is to” がひとかたまりになり “isto” /ɪstə/ のように聞こえることがあり、はっきり区切って “is” と “to” を発音しようとして不自然になるケースもあります。弱形を使うことで自然なリズムになります。
8. 学習上の注意点・よくある間違い
- スペルミス: “is” と “in” の混同はあまりないと思われますが、タイピングミスに注意。
- 同音・類似表現との混同: “It is to be noted that…” のような正式表現でしばしば使われるとき、文の構造が複雑になるので混乱しがちです。
- 試験対策や資格試験での出題傾向:
- 英文法問題で「be to + 動詞の原形」の用法を問う設問が多いです。特に大学入試や公的試験でも「予定・義務・運命・条件」のどの意味かを区別させる問題が出ます。
- TOEICや英検でも文章整序や文法問題などで見かけることがあります。
- 英文法問題で「be to + 動詞の原形」の用法を問う設問が多いです。特に大学入試や公的試験でも「予定・義務・運命・条件」のどの意味かを区別させる問題が出ます。
9. 記憶に残るヒントやイメージ
- 「“be to” は “(計画や義務) + (実現する動作)” をイメージしてみる」
- “If A is to B” → 「もしAがBするつもりなら…」という形で、将来に対する条件や方向性を示すことをイメージしましょう。
- ニュース記事や公的アナウンスで “He is to …” と見たら、「(正式・確定された)予定や義務なんだな」と思い出すと覚えやすいです。
以上が “is to” (be to 構文)の詳細な解説です。この表現を見て、予定・義務・運命・条件という様々な意味合いを汲み取れるようになると、英語の文章を深く理解しやすくなります。ぜひ参考にしてみてください。
意味のイメージ
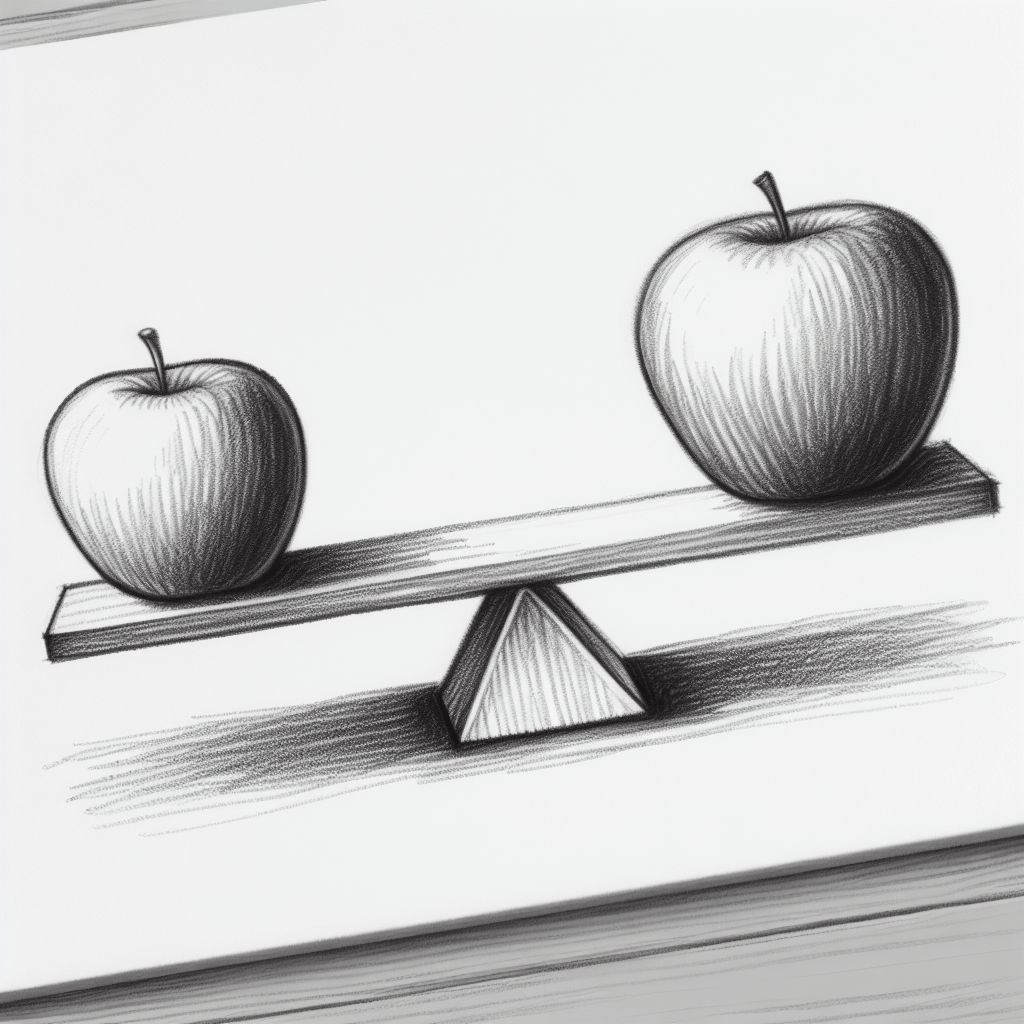
意味(1)
《意志》...するつもりである
意味(2)
《運命》...する運命にある
意味(3)
《義務》...しなければならない
意味(4)
《可能》...できる
意味(5)
《書》《予定》...することになっている
復習用の問題
《書》《予定》...することになっている / 《意志》...するつもりである / 《運命》...する運命にある /《義務》...しなければならない / 《可能》...できる
英語 - 日本語

項目の編集設定
- 項目の編集権限を持つユーザー - すべてのユーザー
- 項目の新規作成を審査する
- 項目の編集を審査する
- 項目の削除を審査する
- 重複の恐れのある項目名の追加を審査する
- 項目名の変更を審査する
- 審査に対する投票権限を持つユーザー - 編集者
- 決定に必要な投票数 - 1
例文の編集設定
- 例文の編集権限を持つユーザー - すべてのユーザー
- 例文の編集を審査する
- 例文の削除を審査する
- 審査に対する投票権限を持つユーザー - 編集者
- 決定に必要な投票数 - 1
問題の編集設定
- 問題の編集権限を持つユーザー - すべてのユーザー
- 審査に対する投票権限を持つユーザー - すべてのユーザー
- 決定に必要な投票数 - 1






